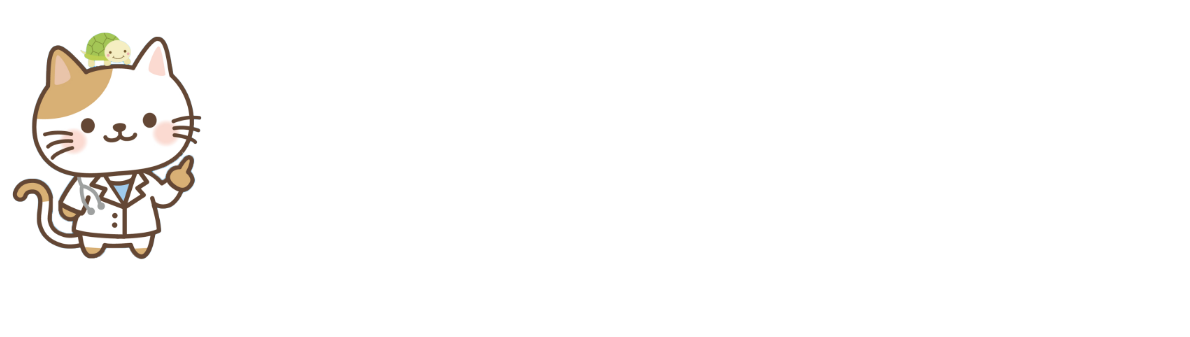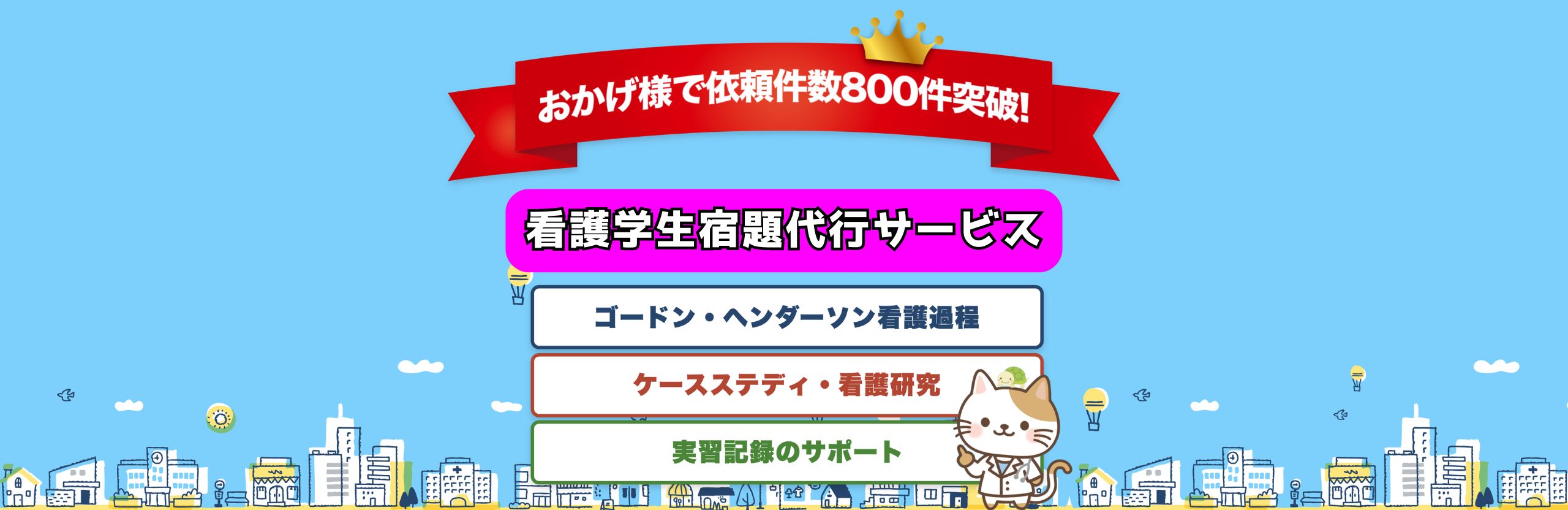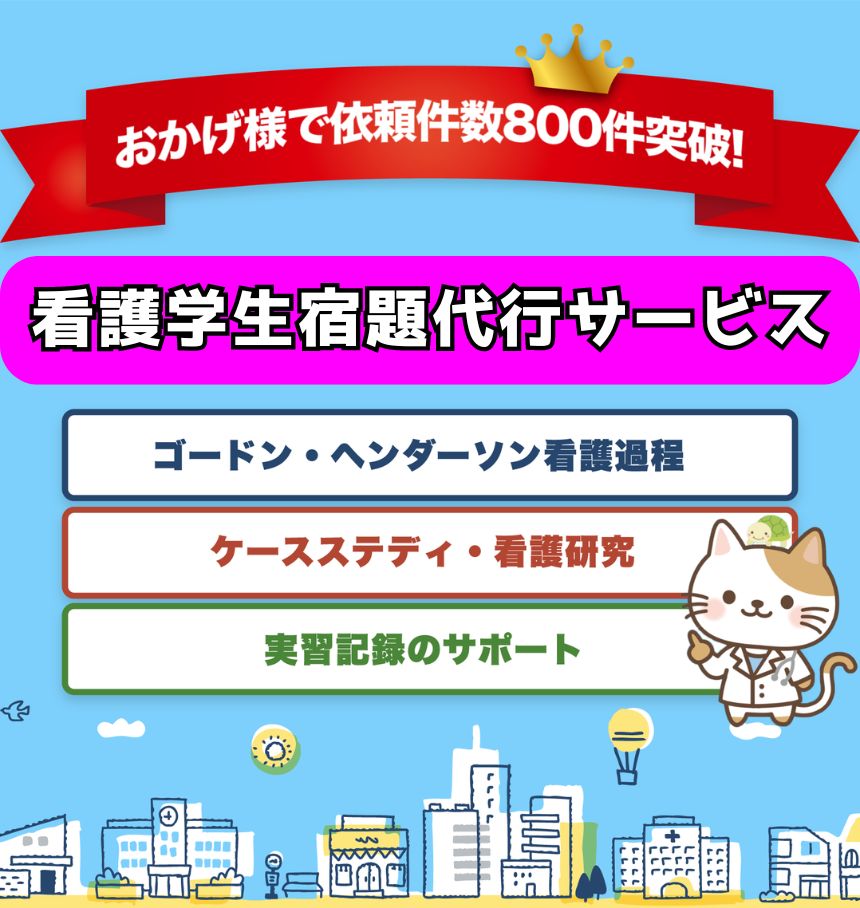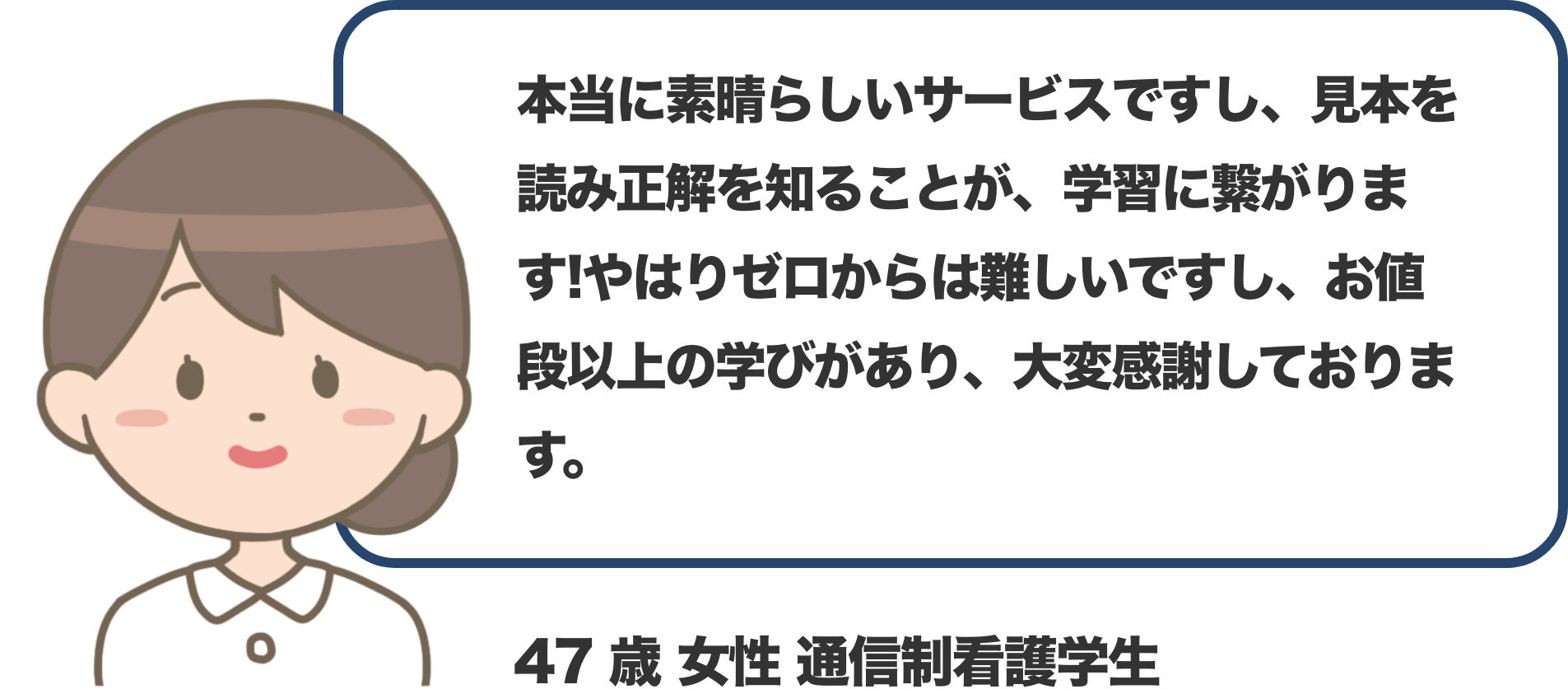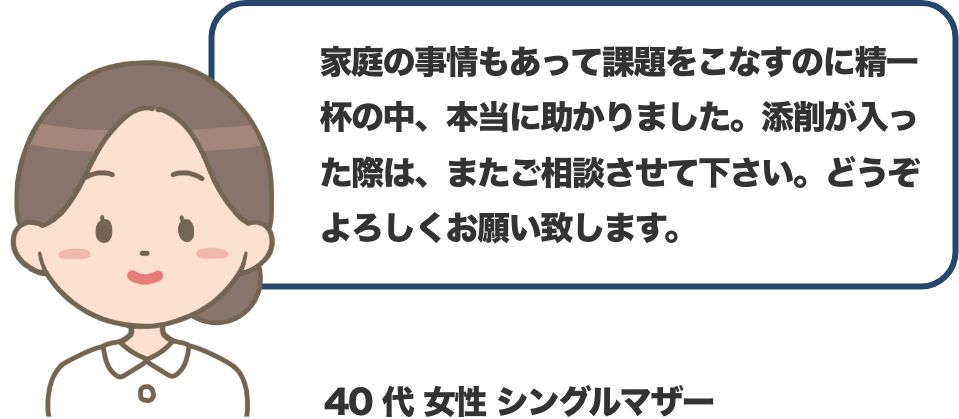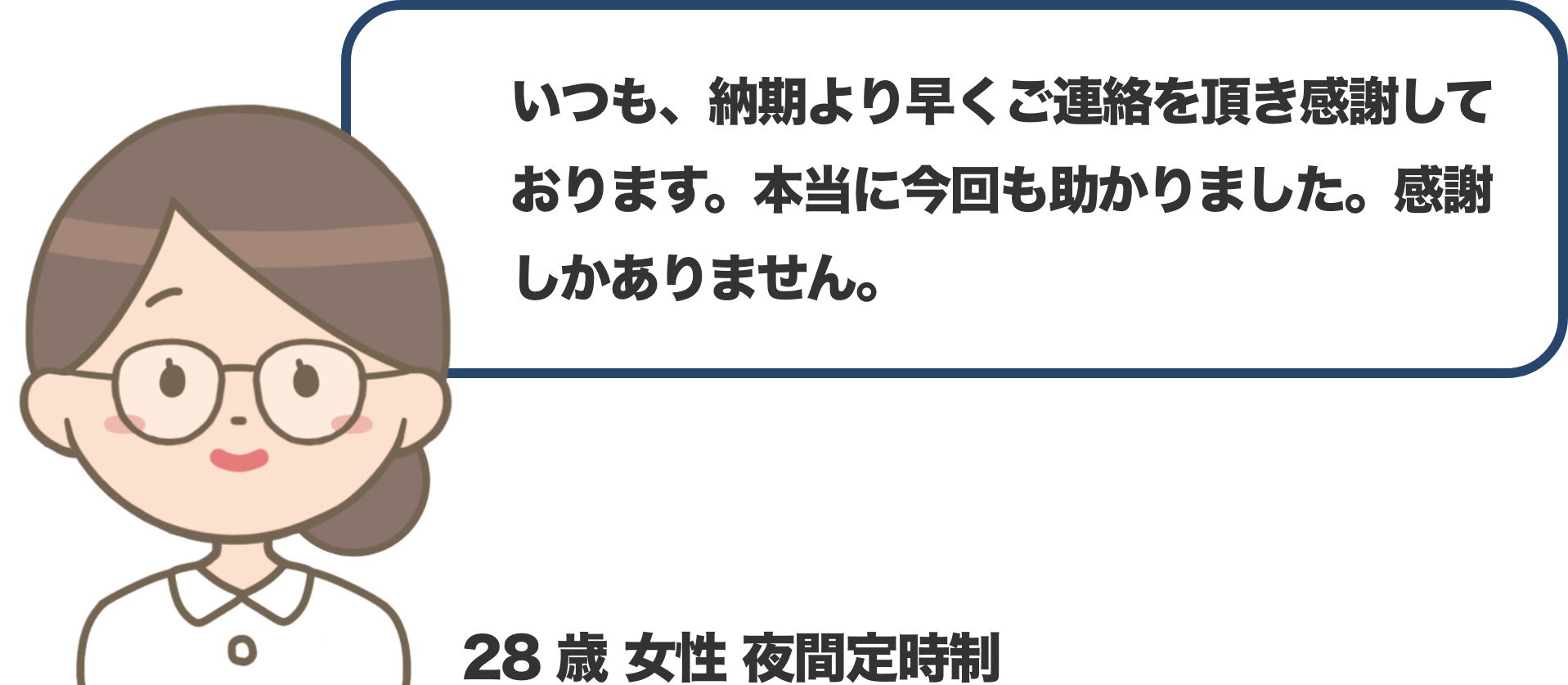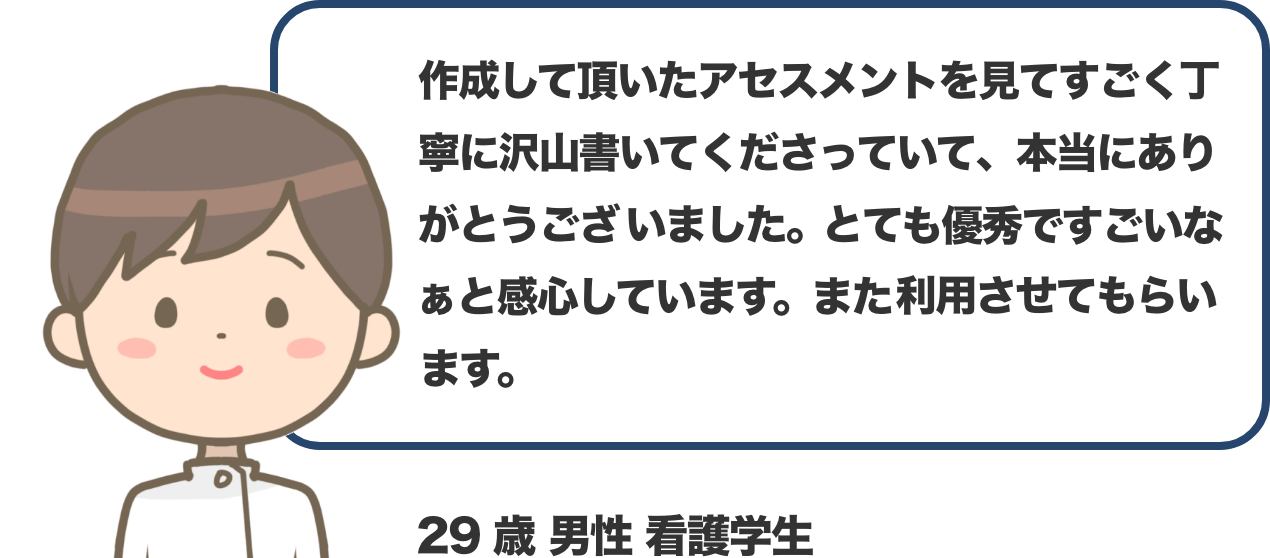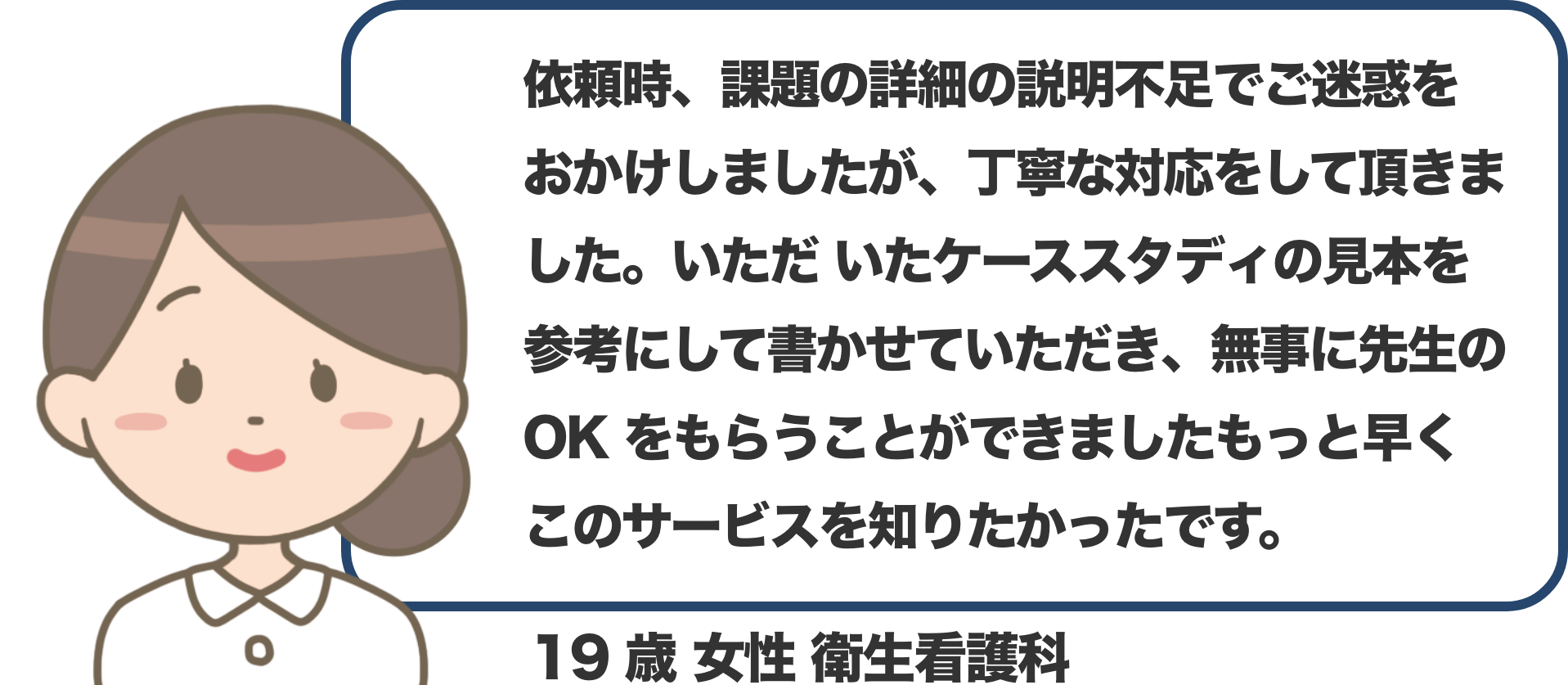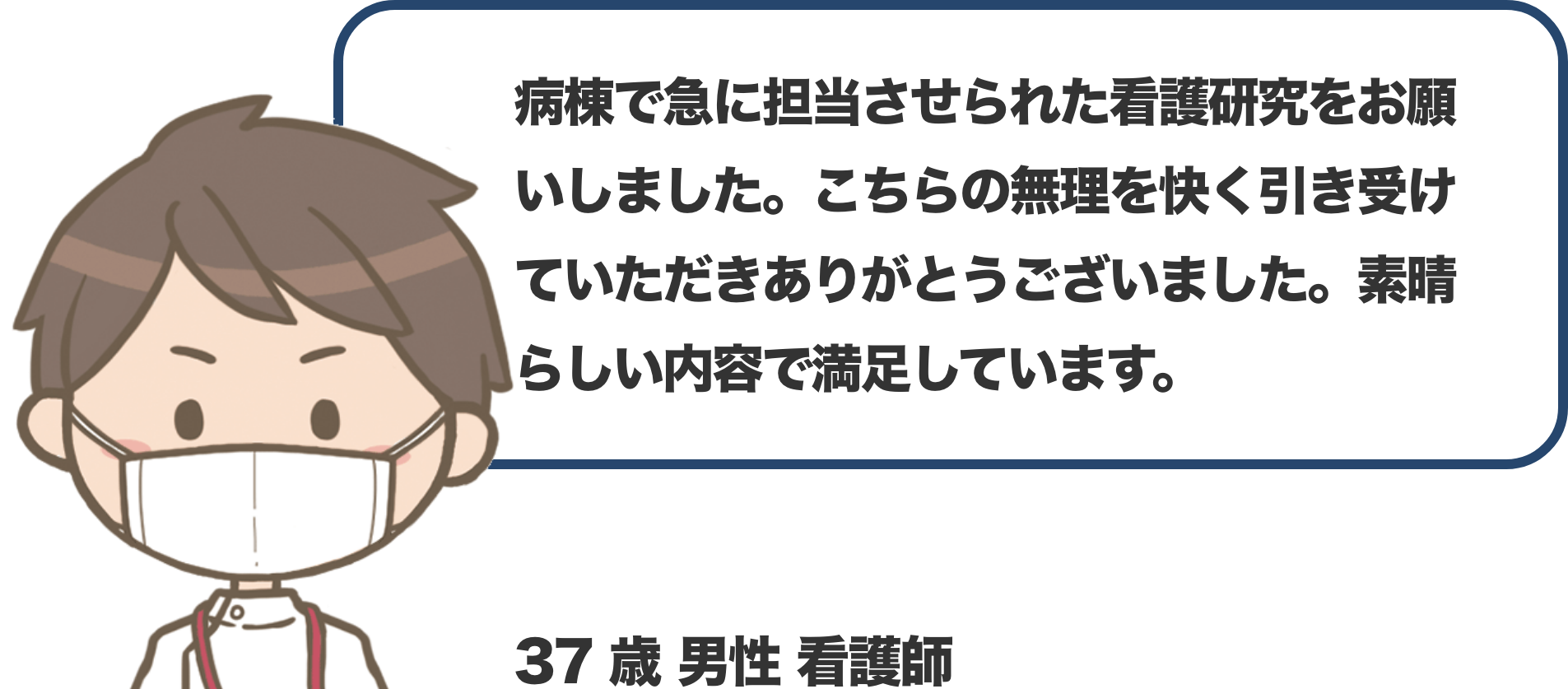目的
- 全身の代謝機能を低下させ、エネルギーの消耗を少なくさせる
- 障害部位の安静をたもつことにより、疼痛を緩和する
- 感染症の患者の場合、循環器の活動を抑制することにより、感染症の疾患が全身に広がるのを少なくする
安静の種類
必要な安静の程度によって絶対安静、床上安静などに分けられる。
安静の程度による段階を安静度という、安静度は疾患別、重症度別に考えられれており、安静度ごとの日常生活行動を中心にした活動の程度の目安が安静度表として示されている。
安静度は疾病の種類や病状に応じて医師から指示される
絶対安静
出来るだけ体を動かさない状態で、日常生活のすべてを援助する。
頭部外傷、脳血管障害の発症直後、心筋梗塞の発症直後など、意識の有無にかかわらず、その症状にあわせて指示される
床上安静
臥床の状態なら自由に身体を動かしてもよい。
また食事、排泄、洗面、読書などの一部は自分で行うことが許可される。
その許可の程度によって、さらに何段階かに分けられる。
その他の安静度
離床が許可される距離(例えばベッド周囲のみ:病室内可、病棟内可)や、自分で実施することが許可される日常生活動作の範囲(例えば洗面、排泄のみ歩行可、洗髪可、入浴可)などにより、何段階かに分けられている
注意点 留意点
- 患者に安静の必要性と安静度の具体的内容を十分に説明し、理解・協力が得られるようにする
- 看護師は指示された安静度の内容をよく理解して、身体的活動が制限されていても患者のニーズが十分に満たされるよう、基本的な日常生活行動に対するきめ細やかな援助を行う
- 援助に際しては個々の患者の安静度に適した方法を工夫し、実施中は常に患者の状態を観察しながら行う
- 身体的安静だけでなく精神的安静にも配慮し、面会人への注意や協力の依頼をする
- 患者の精神的安静を阻害する大きな要因として、不安があるので、看護師は患者の不安を出来るだけ緩和するよう援助する

看護サポート
宿題が多くて悩んでいる看護学生(看護師)さんへ
看護学生宿題代行サービスでは、そんな看護学生(看護師)さんの宿題を代行するサービスを行っています。
ゴードン・ヘンダーソン看護過程(紙上事例)の代行や看護レポート代行、実習記録代行、ケーススタディ代行を行っています。
具体的なご利用方法について知りたい方や宿題代行を希望される方は、下記のLINEボタンからご連絡ください。