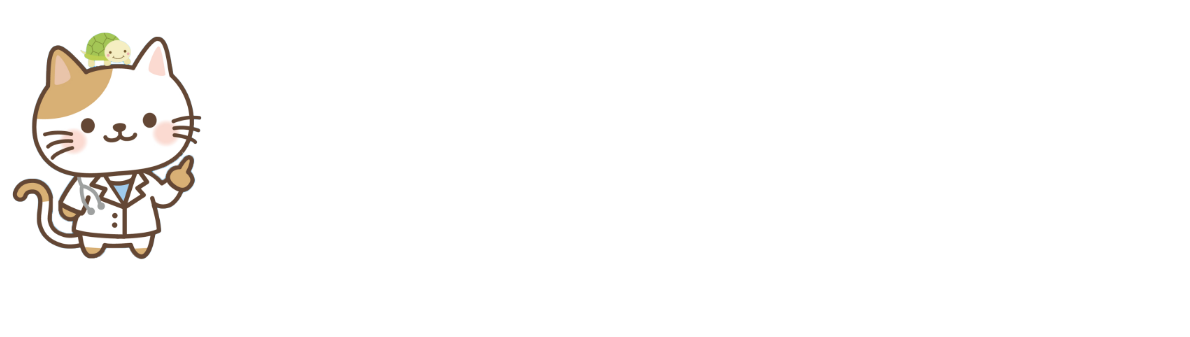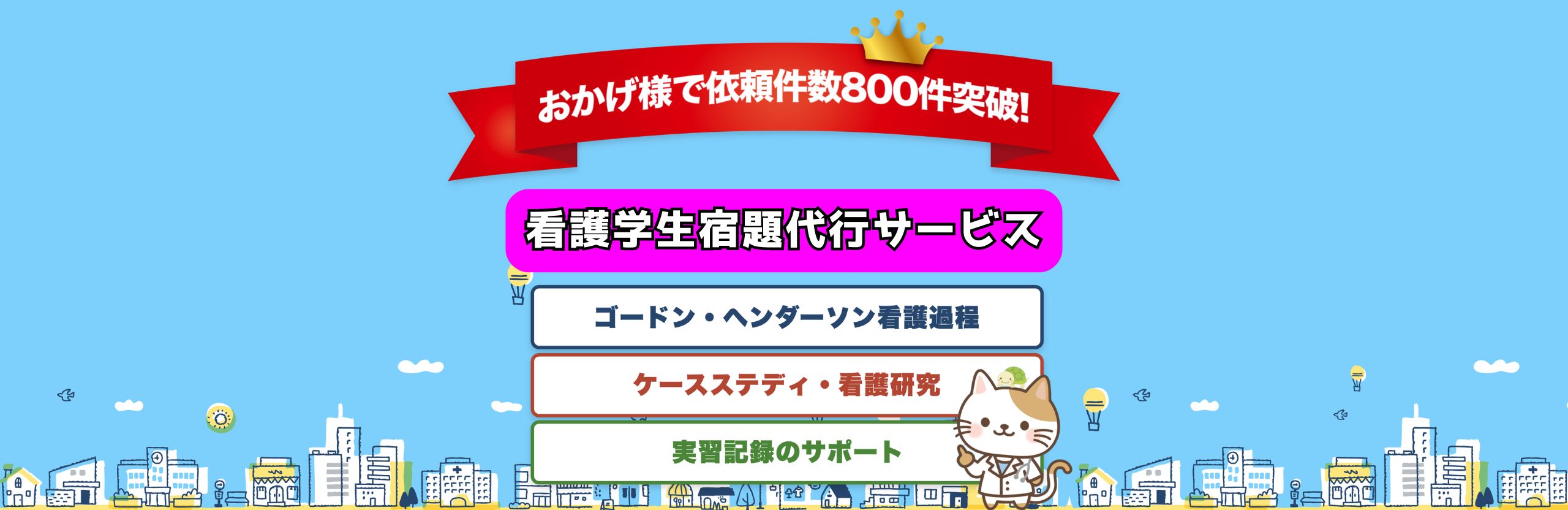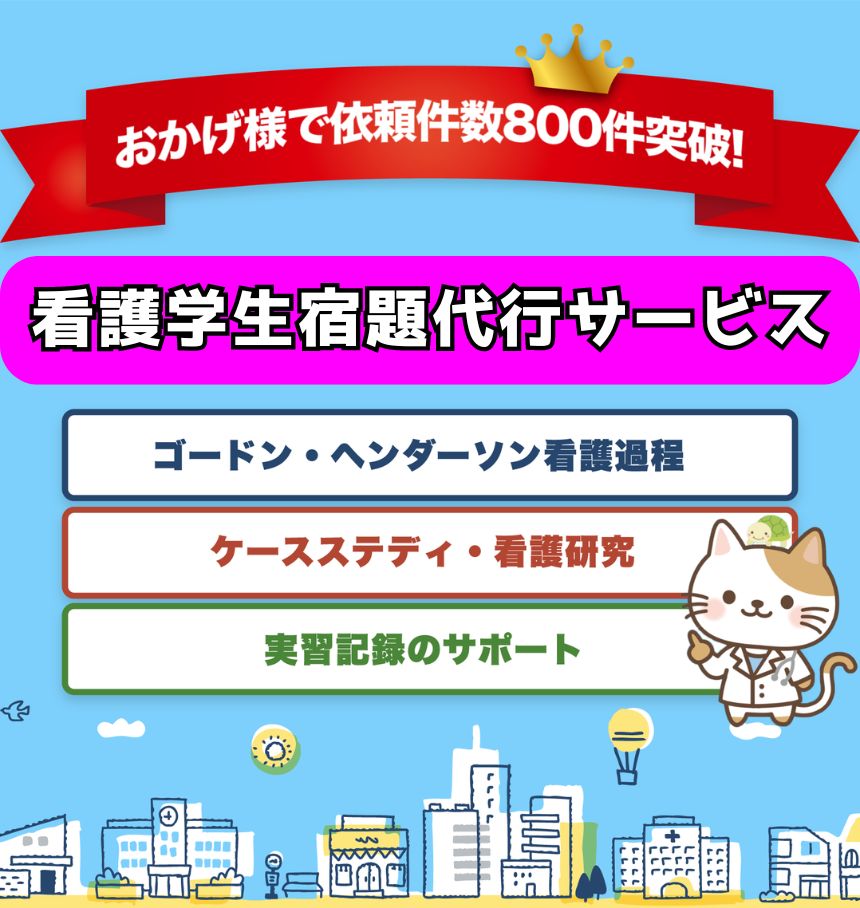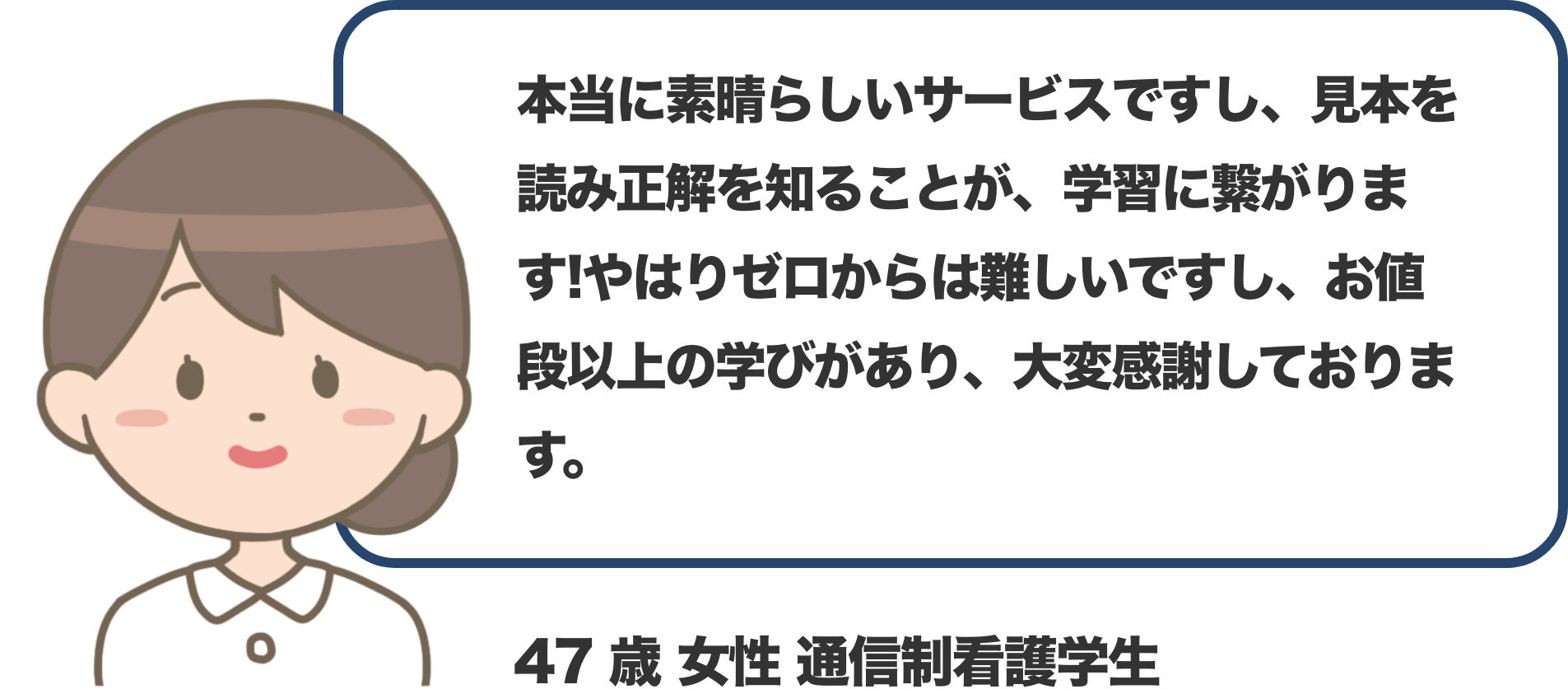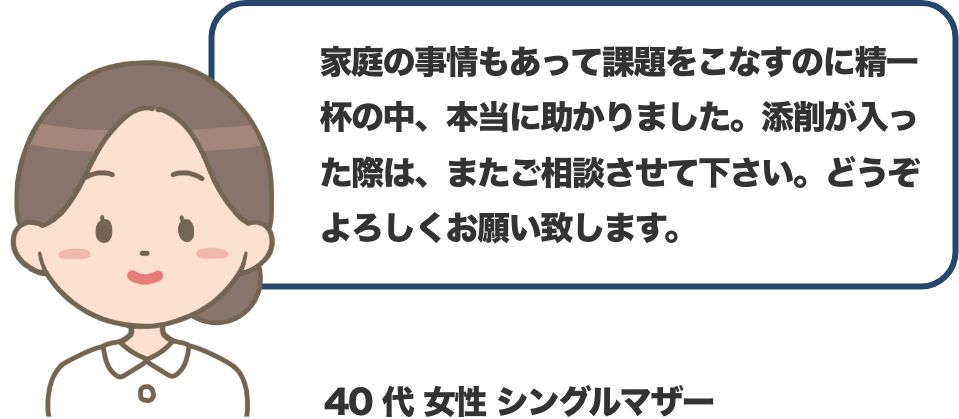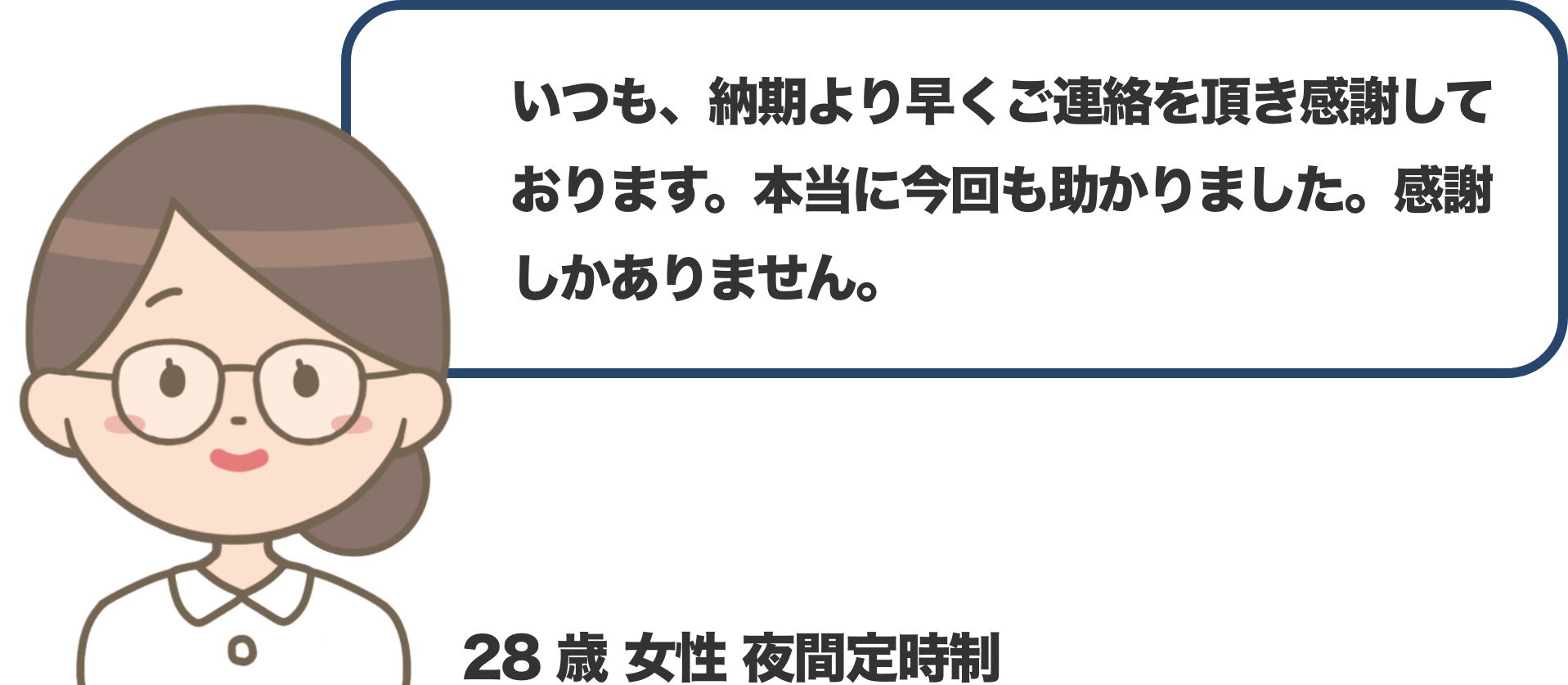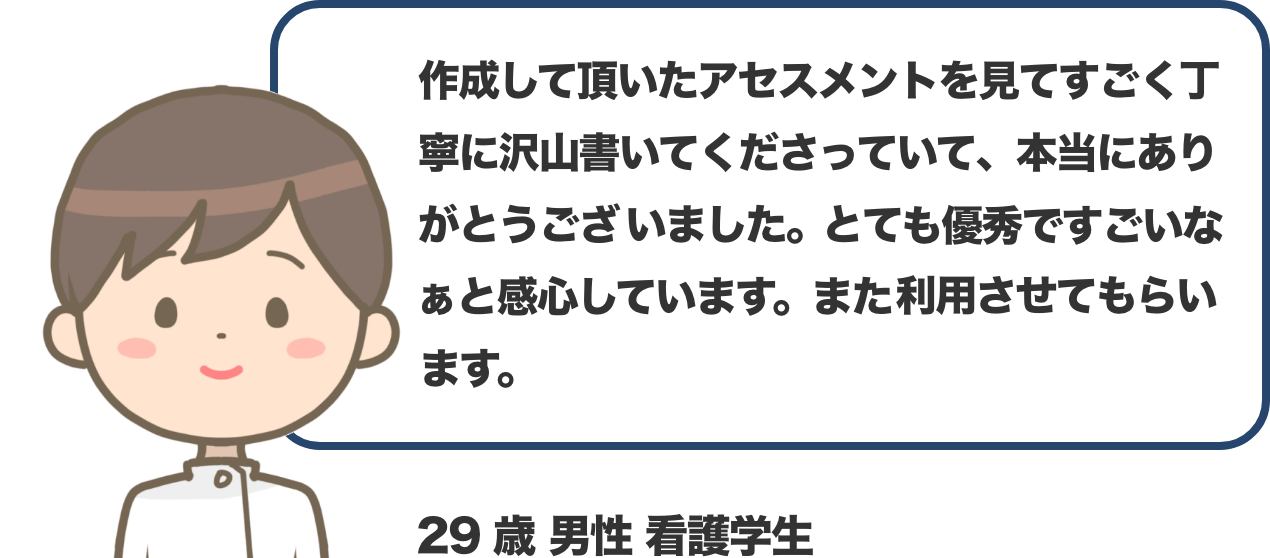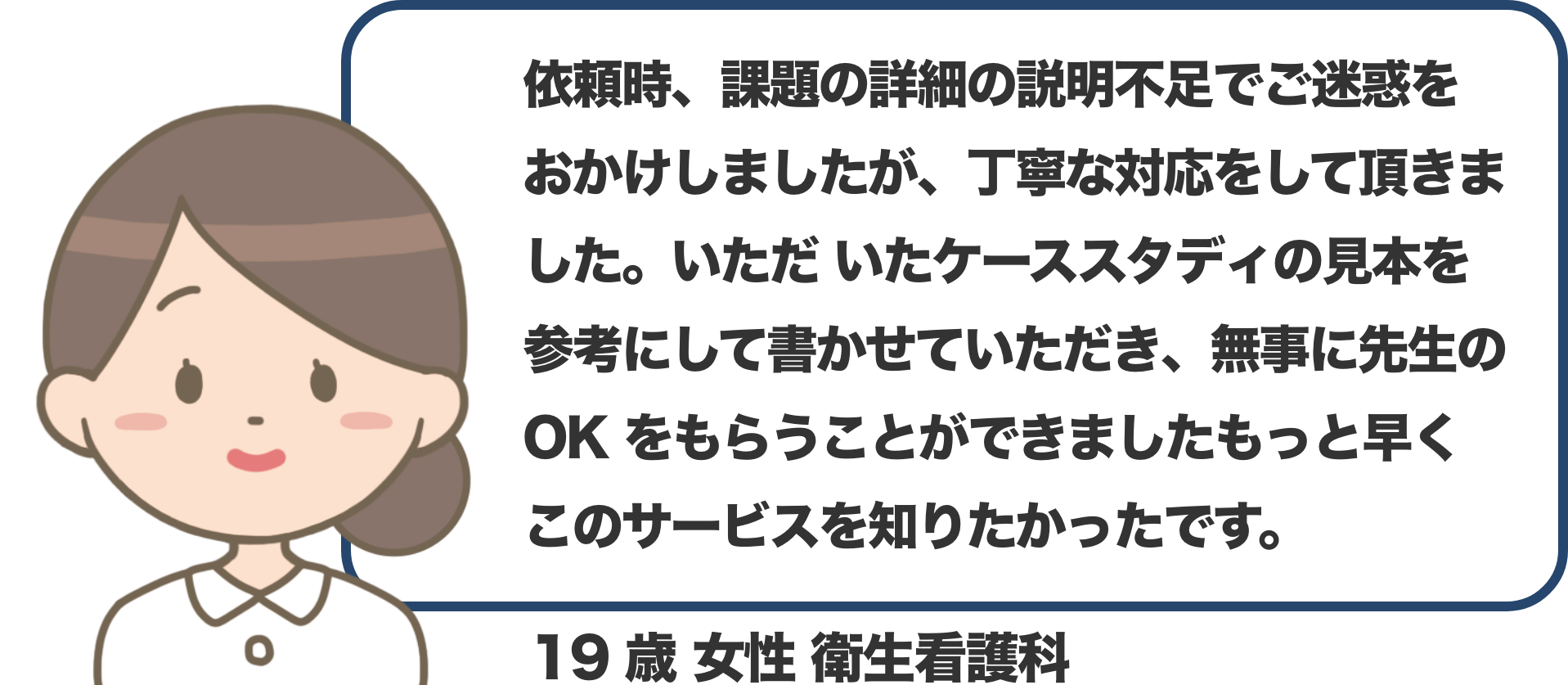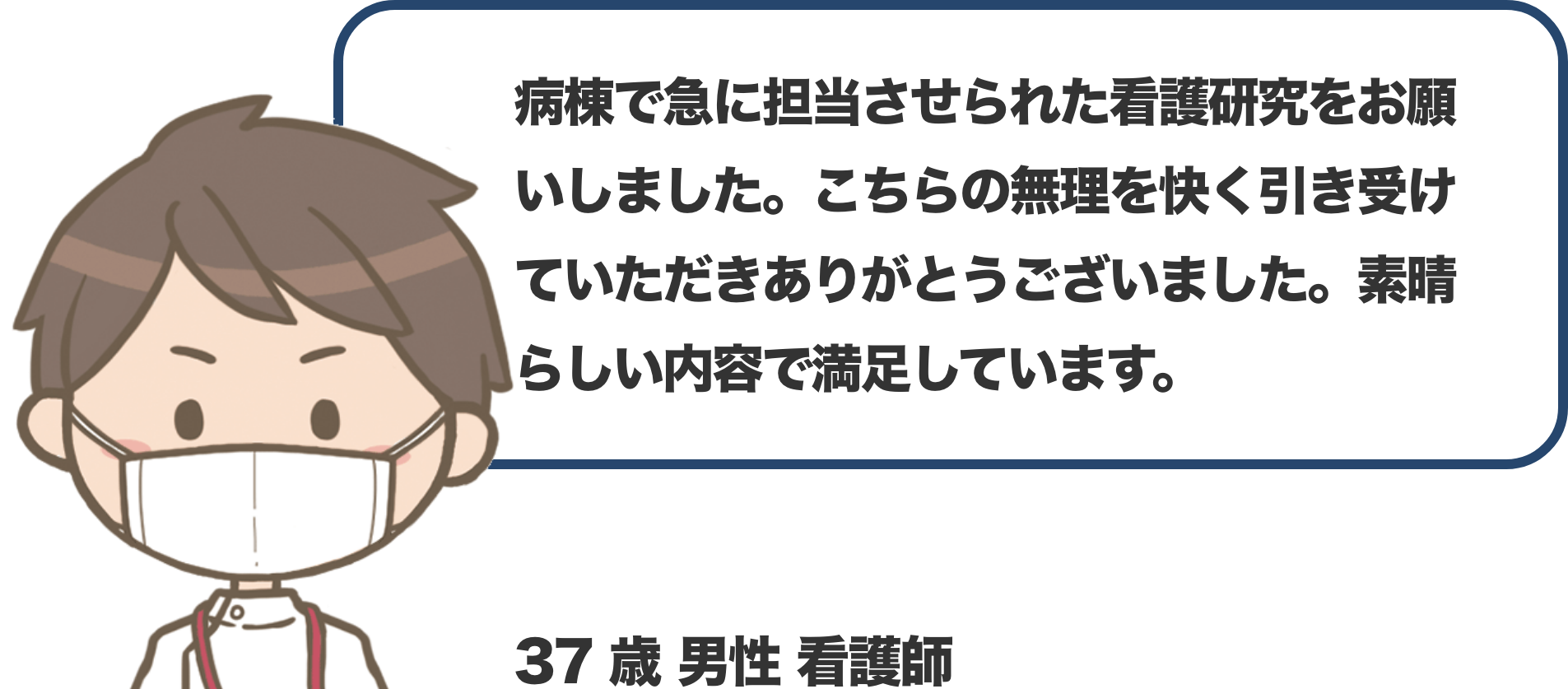病態生理
気道の炎症により粘膜が障害された結果、神経が露出して外の空気に対して過敏に反応している状態。
基本的には時間の経過や薬剤の使用によっておさまるが、発作を繰り返すと治らないタイプの喘息に移行する。
原因としてはアトピーになりやすいアレルギー体質の人に多い。
喘息発作の誘因はハウスダストやダニ、ウイルスなどへの感染、大気汚染、ストレスがある。
また、発作は夜間が多く、昼は少ない。これは睡眠時に気管支が収縮するという人間本来の習性があるためである。
大人は3%の有病率であり、大人になってから罹患すると基本的に一生治らない確立が高い。ただ、ステロイドの使用により一時的に抑えることはできる。
小児の場合は7~8%の有病率があり、成長につれて治っていく場合が多い。
治療法は重症度によって違う。
初期は気管支拡張薬や吸入ステロイドなどを使用する。
貼り薬であるツロブテロール、ホクナリンテープも使用する。
また、ロイコトリエン拮抗薬やプレドニン等の内服ステロイドは中等度や重症患者には多用される。
これらは副作用が多く、医師は慎重に使用するようガイドラインが設けられている。
気管支ぜんそく患者の看護
喘息発作を起こすことによって患者は当然ながら息苦しさを感じる。
また、夜間に発症しやすいことから、睡眠が障害される。
また、家族がそばで寝ている場合は咳をするにも気を使ってしまう。
さらに、いつまでこれが続くのだろうか?
といった不安が重圧としてのしかかる。
ぜんそくはもはや気道だけの問題ではなく重大な精神的不安を巻き起こす起爆剤であると言える。
看護者はそういった患者の気持ちに寄り添うことが大切である。
あとは服薬管理である。
吸入ステロイドなどは3か月~6か月ほど連続使用しないと効果が無い。
なので、休まずに毎日してもらうことが大切だ。