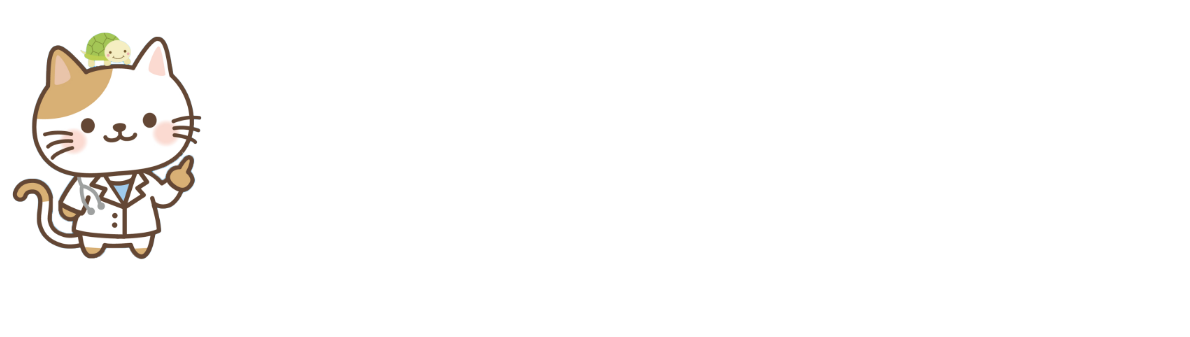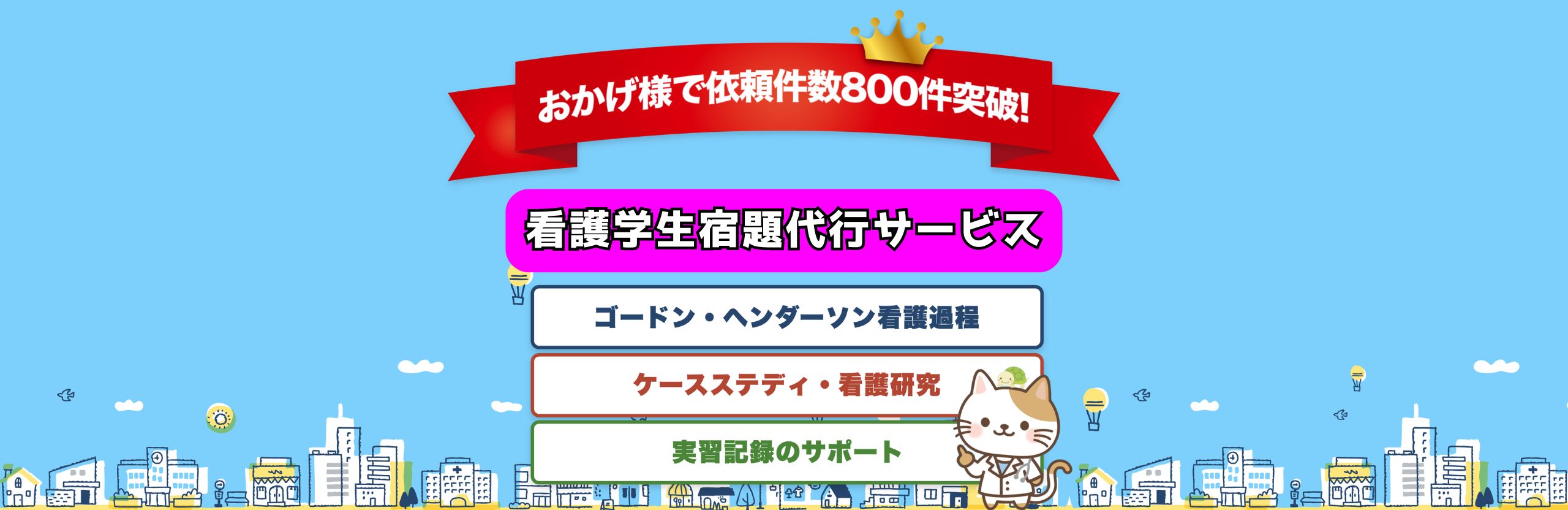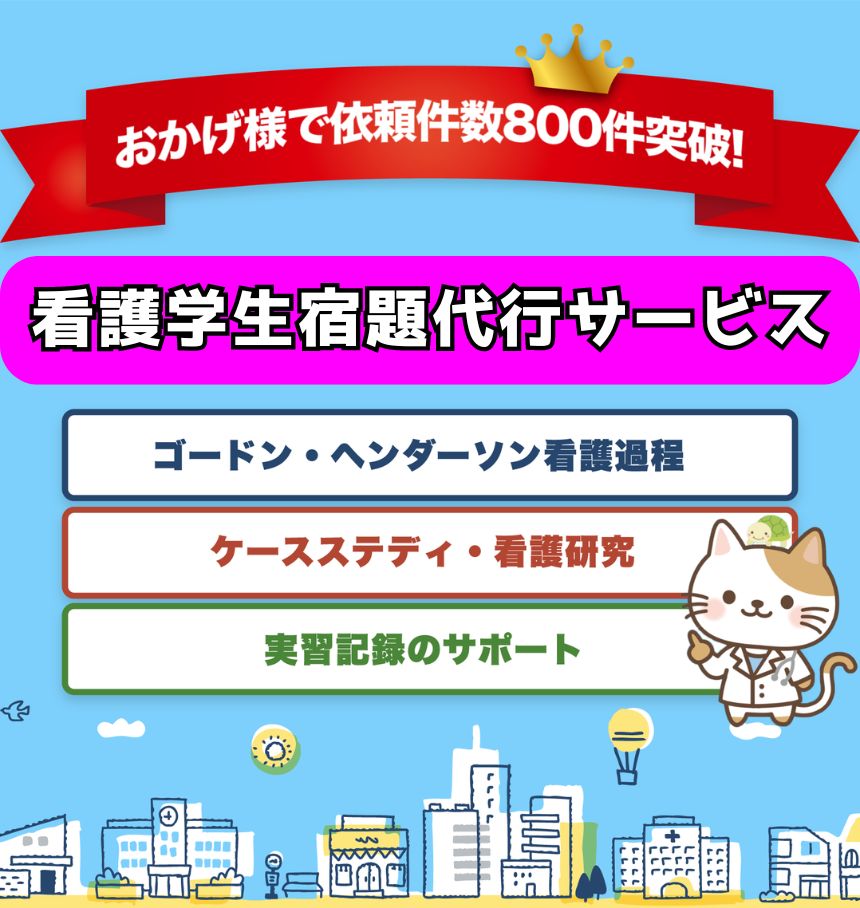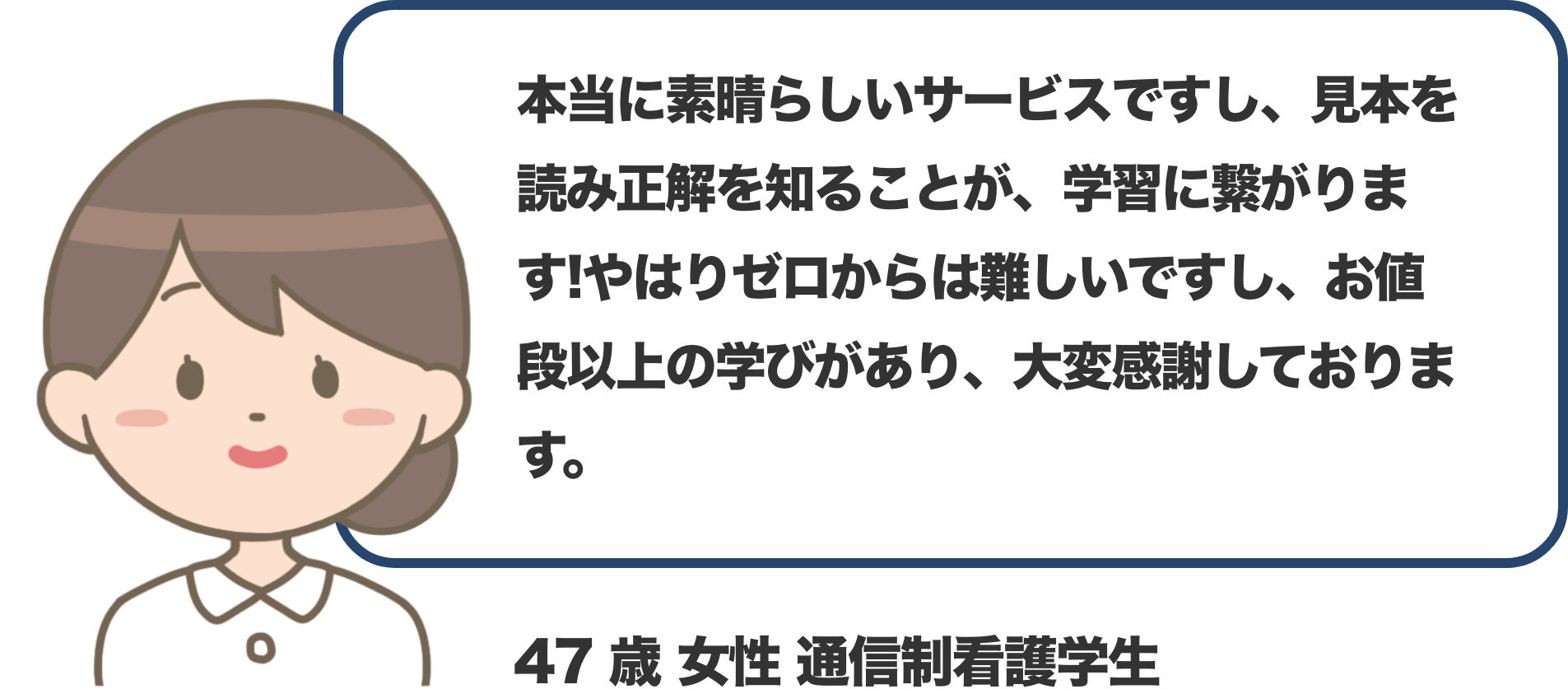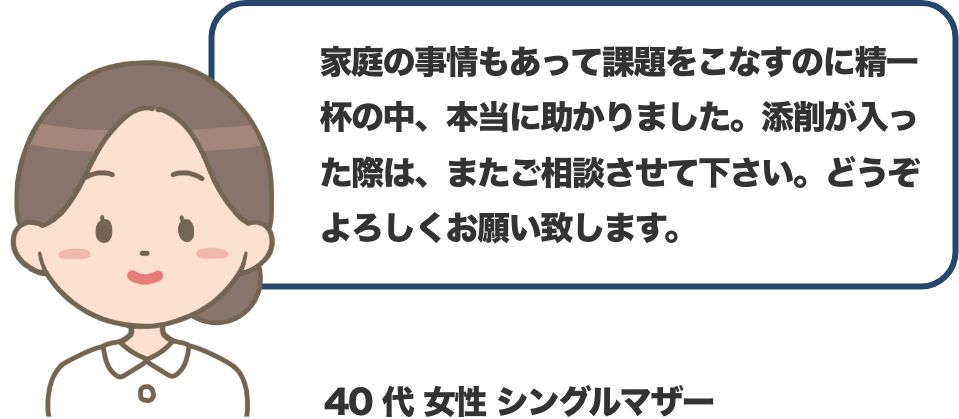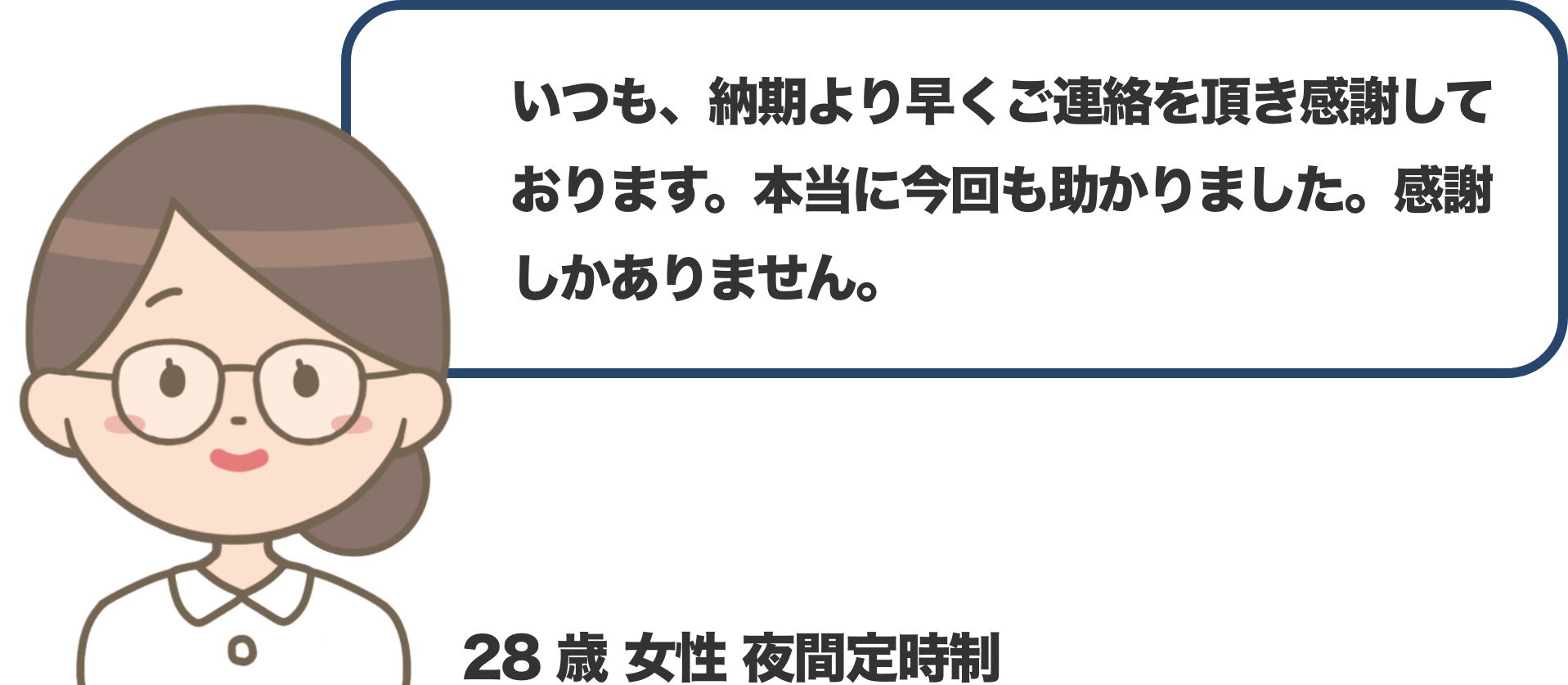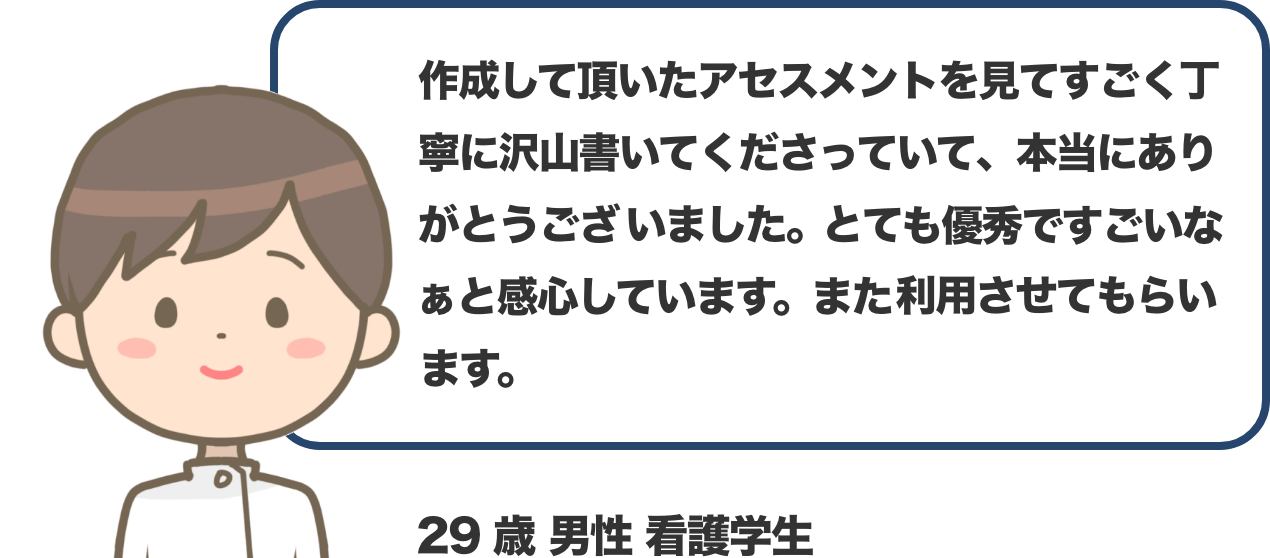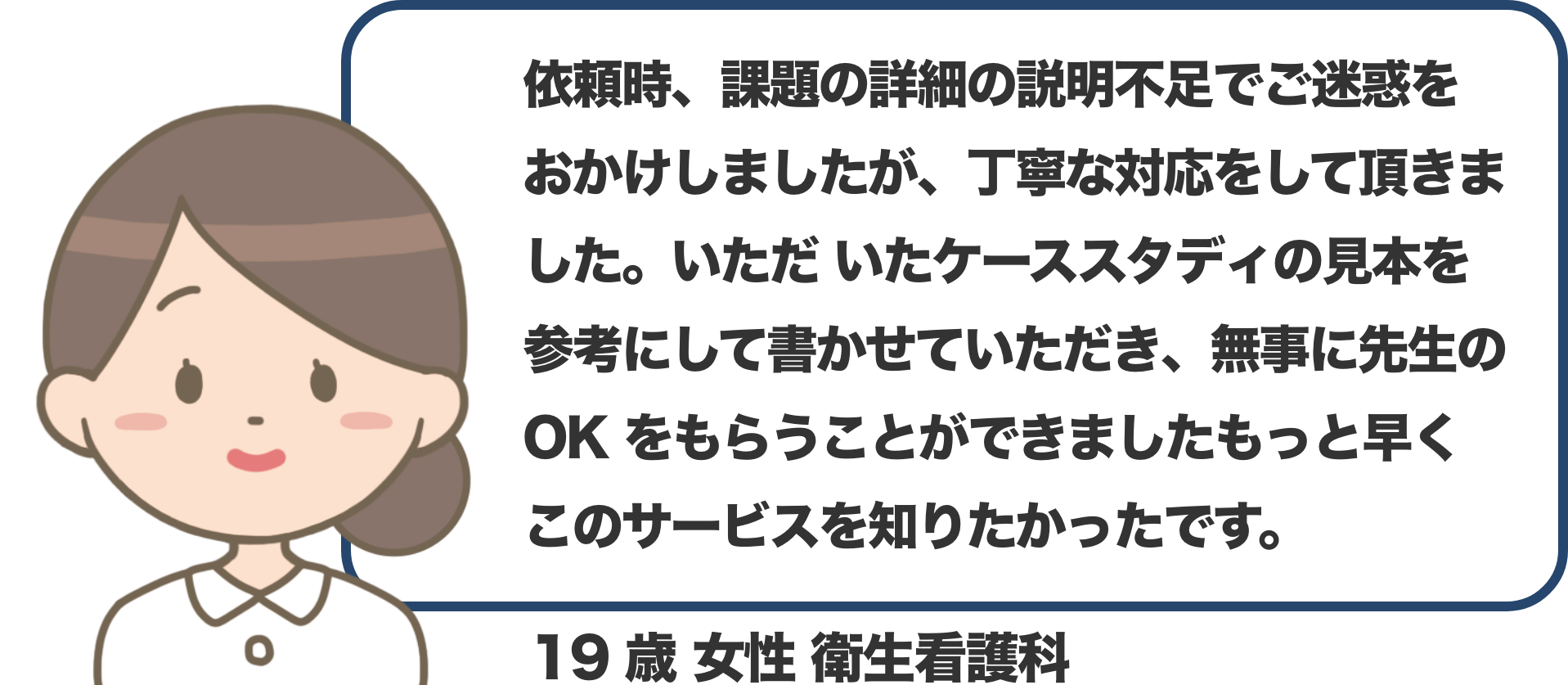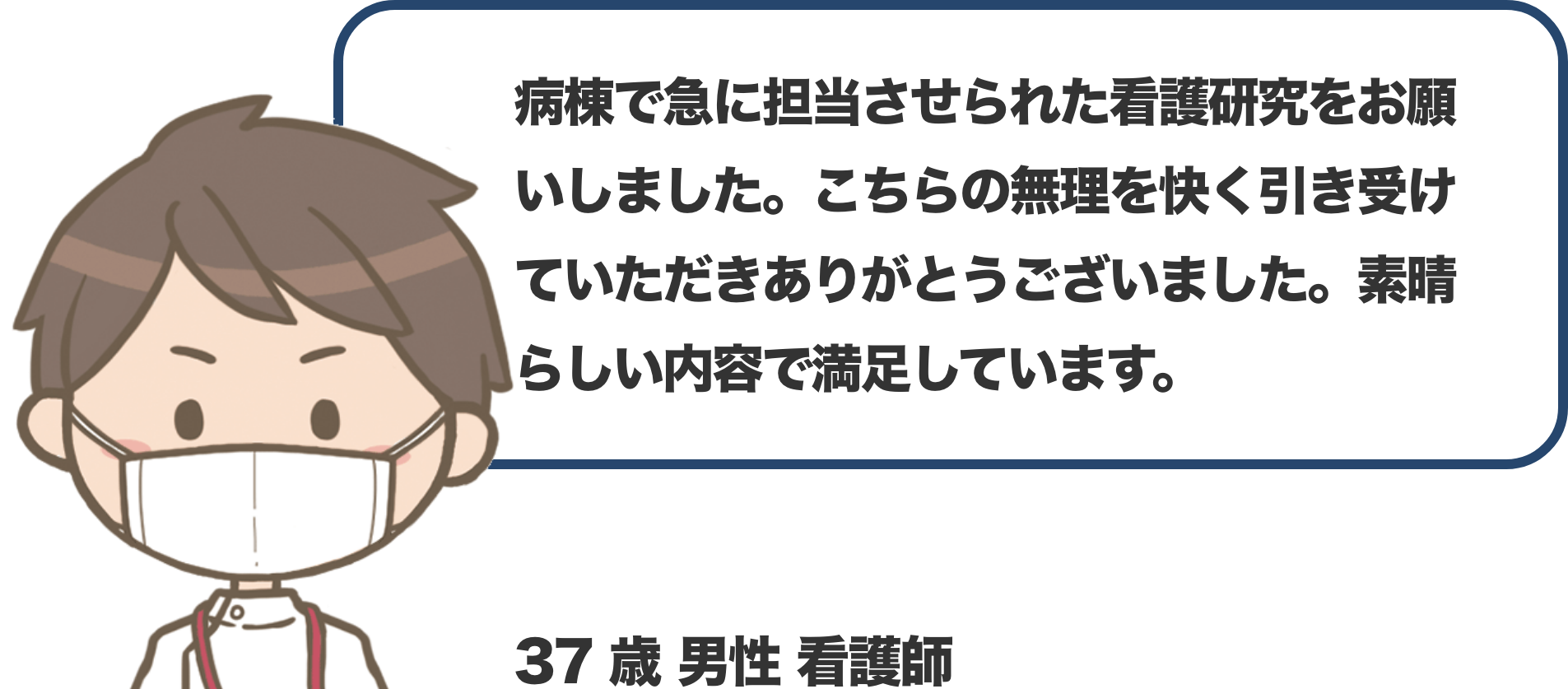看護目標
- 服薬コンプライアンスを向上させ、ADLを保持できるようにする。
- リハビリテーションを行い、ADL機能の維持・向上を目指す。
- 長期臥床による合併症予防のため、ADLの維持・向上を図る。
- 疾病と障害を受容し、変化が認められ自分なりの「生き方」ができるようにする。
#1.確実に服薬できないことによる薬の調整不良。
期待される結果
指示量を服薬時間に確実に内服できる。
OP
抗パーキンソン薬の内服、副作用(幻覚、妄想、精神症状)の有無。
薬効のモニタリング(日常行動の動き、持続時間、On-Off現象、Wearing-off現象の有無、程度)。
錐体外路症状(筋固縮、無動、振戦、姿勢反射障害)の程度、進行の把握、重症度と障害度の把握(Hoehn-Yahr生活障害度)。
TP
日常生活行動の程度を把握し、患者のペースに合わせて行動する。
抗パーキンソン薬の薬効が自分の動きにどう影響を及ぼしているか理解できる。
薬の服薬時間を生活習慣に合わせる。
薬物の血中濃度の変化によって症状が変動するため、投薬時間の変更を医師とともに検討する。
嚥下困難な患者への内服介助。
EP
疾病の理解や薬物療法の必要性を患者、家族に説明し指導する。
副作用の症状や症状の進行、変動など異常の観察と対処の説明をする。
高蛋白質の摂取で薬効が減弱することの説明。
低蛋白質療法の指導(ビタミンB6による薬理効果減弱)。
#2.錐体外路症状による転倒リスクとADLの維持の困難。
期待される結果
転倒を防止する。
意欲的にリハビリテーションを行えるようになる。
患者のペースに合わせたADLが維持できる。
OP
錐体外路症状がADLに及ぼす影響、日常生活行動レベルの把握。
関節可動域、しびれ感、振戦、四肢筋力、姿勢、歩行の状態。
運動障害の患者の受容段階、反応の仕方や行動パターン。
顔や表情の変化。
TP
転倒防止に注意し、すくみ現象、突進歩行、バランスが悪い、方向転換が困難であることに対処。
環境整備を行い、歩行障害となるものを置かない。
リハビリテーションを計画的に行う。
患者自身の活動を確認し、できることから進め、患者に代わってセルフケアを満たす行為を患者と相談しながら行う。
寝たきりにならないように、全身管理と関節可動域の運動は計画的に行う。
本人の意思を尊重し、自信が持てるように援助する。
患者の症状は個人差があり、一日の健康状態が異なる疾患であるため、状態に合わせてアプローチしていく。
せかさずにゆっくりと患者のペースに合わせる。
EP
リハビリテーションの効果について説明し、コミュニケーションをとりながら励ます。
自分でできる日常生活行動は行っていくように指導する。
患者が「生きがい」を見つけられ、生活設計が立てられるように家族とともに支援していく。
在宅環境が整えられるように家族への支援態勢の説明をする。
転倒予防対策として、方向転換時に弧を描くように移動、遠くに手を伸ばす動作の回避など、具体的な生活指導をする。
#3.病状の進行に伴い合併症を起こしやすい。
期待される結果
誤嚥性肺炎を起こさない。
イレウスを起こさない。
尿路感染症を起こさない。
脱水を起こさない。
褥創ができない。
OP
誤嚥性肺炎の徴候(嚥下機能、肺雑音、痰喀出の有無、呼吸数、喘鳴)。
発熱、血液データ、血液ガス、胸部X-P。
イレウス徴候の観察(自律神経障害による排便、排尿障害の有無、腸蠕動の有無)。
食欲状況、食事摂取量、嘔気、嘔吐の有無、便の性状、体重減少の有無。
ADL活動状況、褥創の有無。
TP
脱水状態(水分バランス、尿量、尿比重)にしない、必要時輸液管理。
肺理学療法(ネブライザー、吸入、体位変換)。
食事の誤嚥に注意し、体位はファーラー位とする。
排便コントロールをする(飲水、繊維の食事、緩下剤の使用)。
EP
病状の説明、理解を確認し処置、ケアの必要性の説明をする。
患者、家族が異常の観察をできるように指導、在宅時対処できるように指導する。
#4.身体機能の低下、外観の変化により精神的な症状が起こりやすい。
期待される結果
疾患の受容ができる。
QOLが向上できる。
OP
機能低下、外観の変化に対する気持ち、動揺。
精神的落胆、抑うつ状態、精神症状、不眠の有無。
家族や友人からの精神的変化の言語、態度(病気以前との比較)。
家族の予後への不安、ストレスの有無。
TP
体動の制限をするのではなく、満足感が得られ自信がもてるように支援する。
外観を気にしないような環境づくりをする。
心理特性に配慮して、生活上の理解をうながす。
今までに経験したことのない症状、機能低下に対して不安に陥ることを察知し、家族の意とともに支援する。
動くことへのこだわりがみられたり、Wearing-off現象、On-off現象の発現頻度も増してきたら転倒に注意する。
EP
リハビリが症状を緩和し、薬物療法によりADL機能の維持向上できることが受容でき、患者自身が自分の「生き方」を見つけられるように、精神的に支援していく。
在宅生活で患者を取り巻く生活環境を充実させるため、家族への支援体制(社会資源の活用、技術、経済、急変時の対処)を考え、家族の負担が最小限になるようにして、患者とともにQOL向上が考えられるように援助していく。

宿題が多くて悩んでいる看護学生(看護師)さんへ
看護学生宿題代行サービスでは、そんな看護学生(看護師)さんの宿題を代行するサービスを行っています。
ゴードン・ヘンダーソン看護過程(紙上事例)の代行や看護レポート代行、実習記録代行、ケーススタディ代行を行っています。
具体的なご利用方法について知りたい方や宿題代行を希望される方は、下記のLINEボタンからご連絡ください。