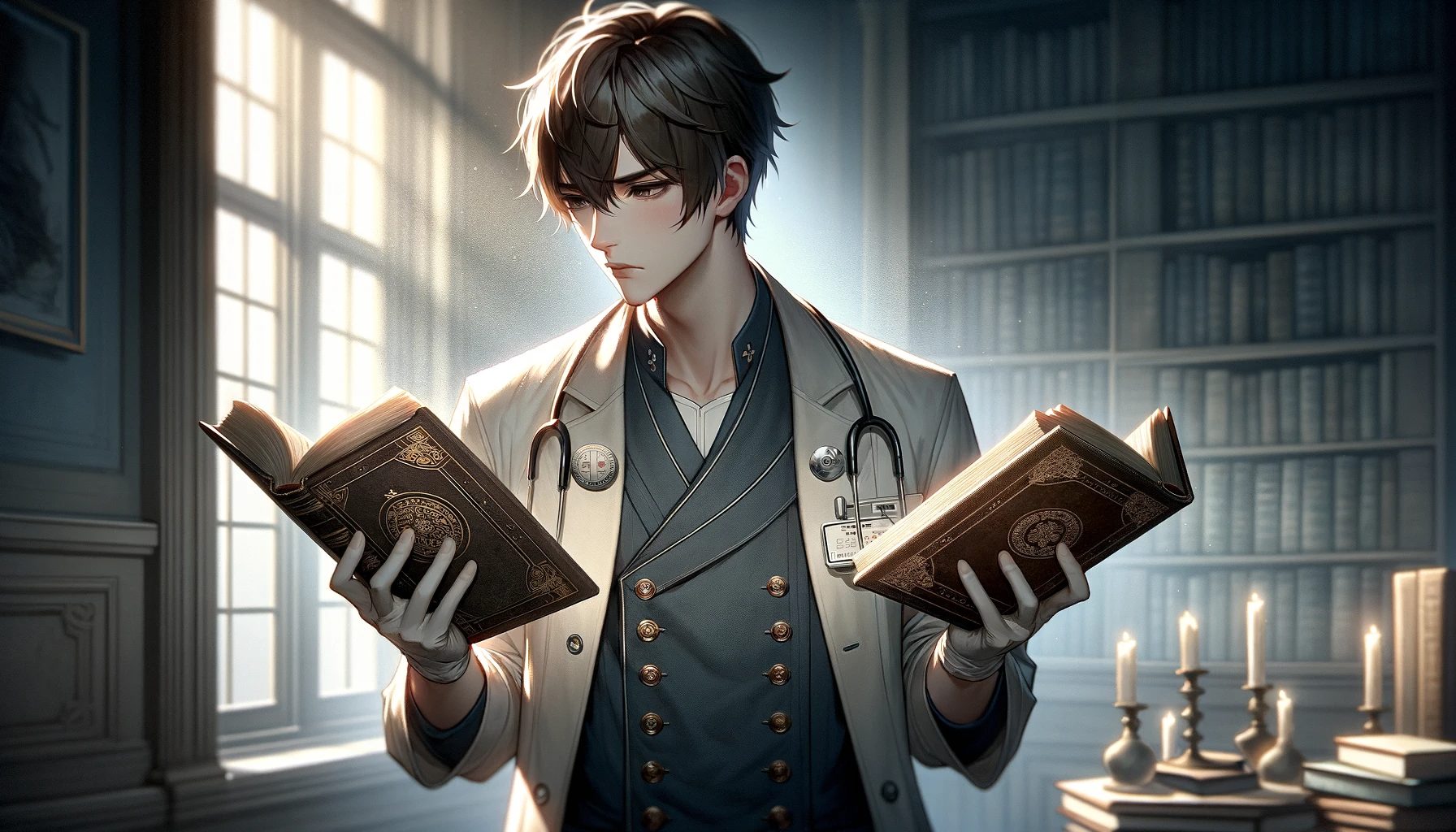カルペニートの看護診断とNANDA-Iの違いについてご紹介します。
まずは起源から
まず、カルペニートの看護診断は、1980年代初頭にアメリカの看護学者マーガレット・カルペニートによって提唱された診断プロセスであり、看護診断の分野で初めて発表された。
一方、NANDA-Iは、1982年にNANDA Internationalとして設立された非営利組織であり、国際的な看護診断分類(Nursing Diagnoses)の開発と普及を目的としている。
次に、診断プロセスについてであるが、カルペニートの看護診断は、看護師が患者の問題やニーズを特定するための質問を提供し、それによって患者の状態を評価し、看護診断を導き出すことが求められる。
一方、NANDA-IIは、診断名を提供することが特徴であり、看護師が患者の状態を評価した後に、該当する診断名を選択することが求められる。
最後に、使用する用語について述べる。
カルペニートの看護診断は、看護師が患者の問題やニーズを評価するために使用する質問に焦点を当てており、一方NANDA-Iは、診断名を提供している点が特徴である。
カルペニートの看護診断とNANDA-Iはどっちが使いやすいの?
カルペニートの看護診断とNANDA-Iはどちらが使いやすいかという点については、状況によって異なる。
カルペニートの看護診断は、看護師が質問を提供して、患者の問題やニーズを評価し、看護診断を導き出す必要がある。
一方、NANDA-Iは診断名を提供することが特徴であり、看護師は患者の状態を評価してから、適切な診断名を選択する必要がある。
方法によって異なるため、どちらが使いやすいかは個人差がある。
看護師が患者の状態を正確に評価し、診断を導き出すことができる場合には、カルペニートの看護診断が使いやすいと言える。
一方、時間が限られている場合や診断名を使用することでコミュニケーションがスムーズになる場合には、NANDA-Iが使いやすいと言える。
つまり、使用目的や状況によって異なるため、どちらが使いやすいかは個人の判断によるということになる。

宿題が多くて悩んでいる看護学生(看護師)さんへ
看護学生宿題代行サービスでは、そんな看護学生(看護師)さんの宿題を代行するサービスを行っています。
ゴードン・ヘンダーソン看護過程(紙上事例)の代行や看護レポート代行、実習記録代行、ケーススタディ代行を行っています。
具体的なご利用方法について知りたい方や宿題代行を希望される方は、下記のLINEボタンからご連絡ください。