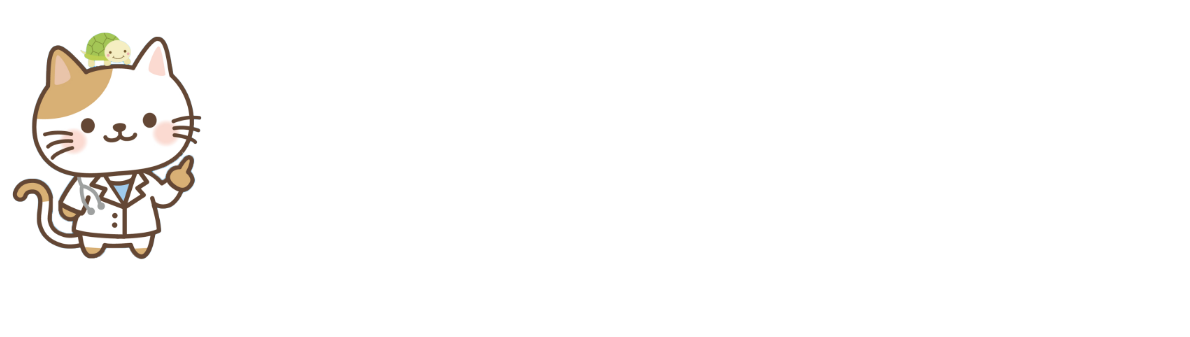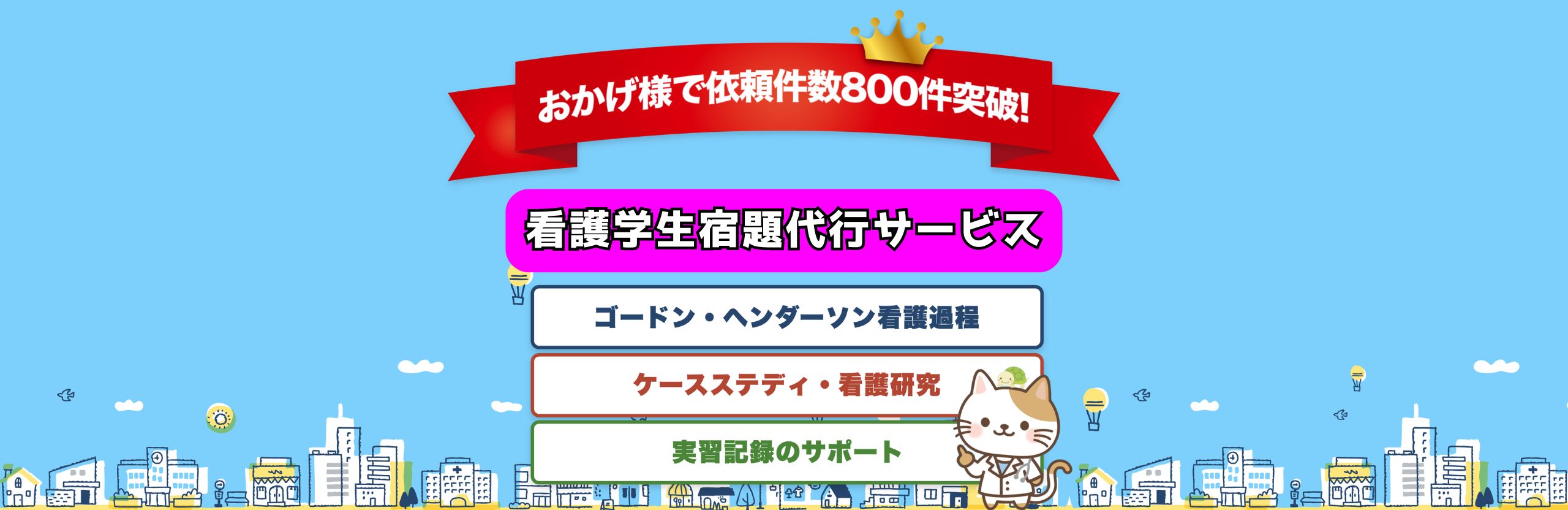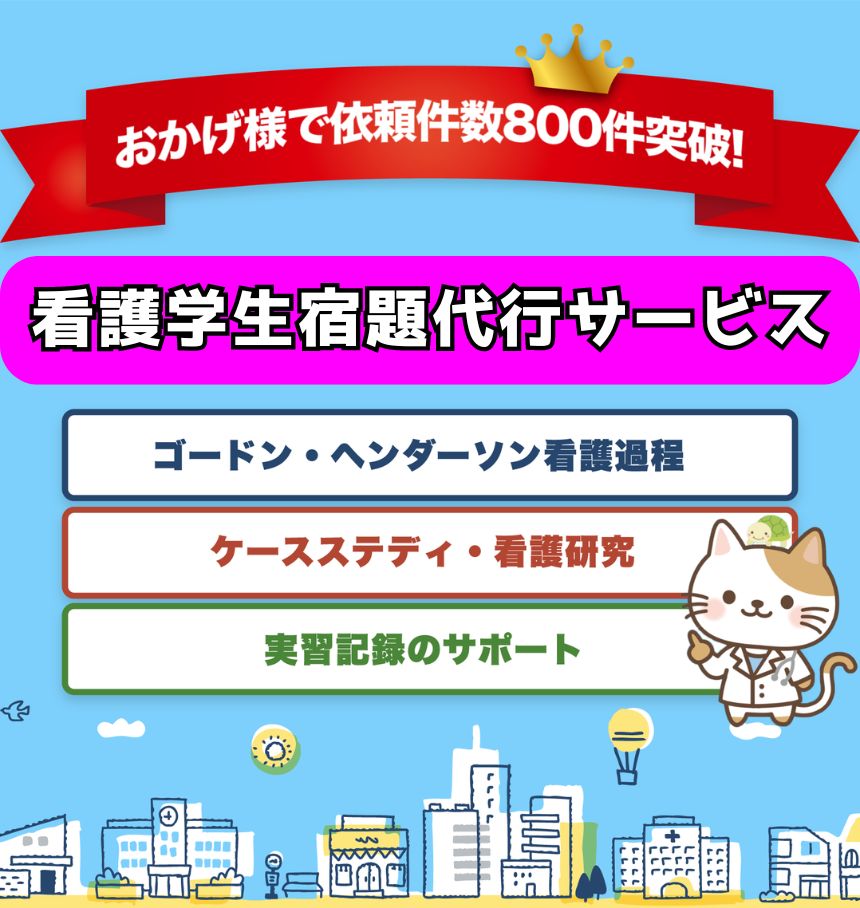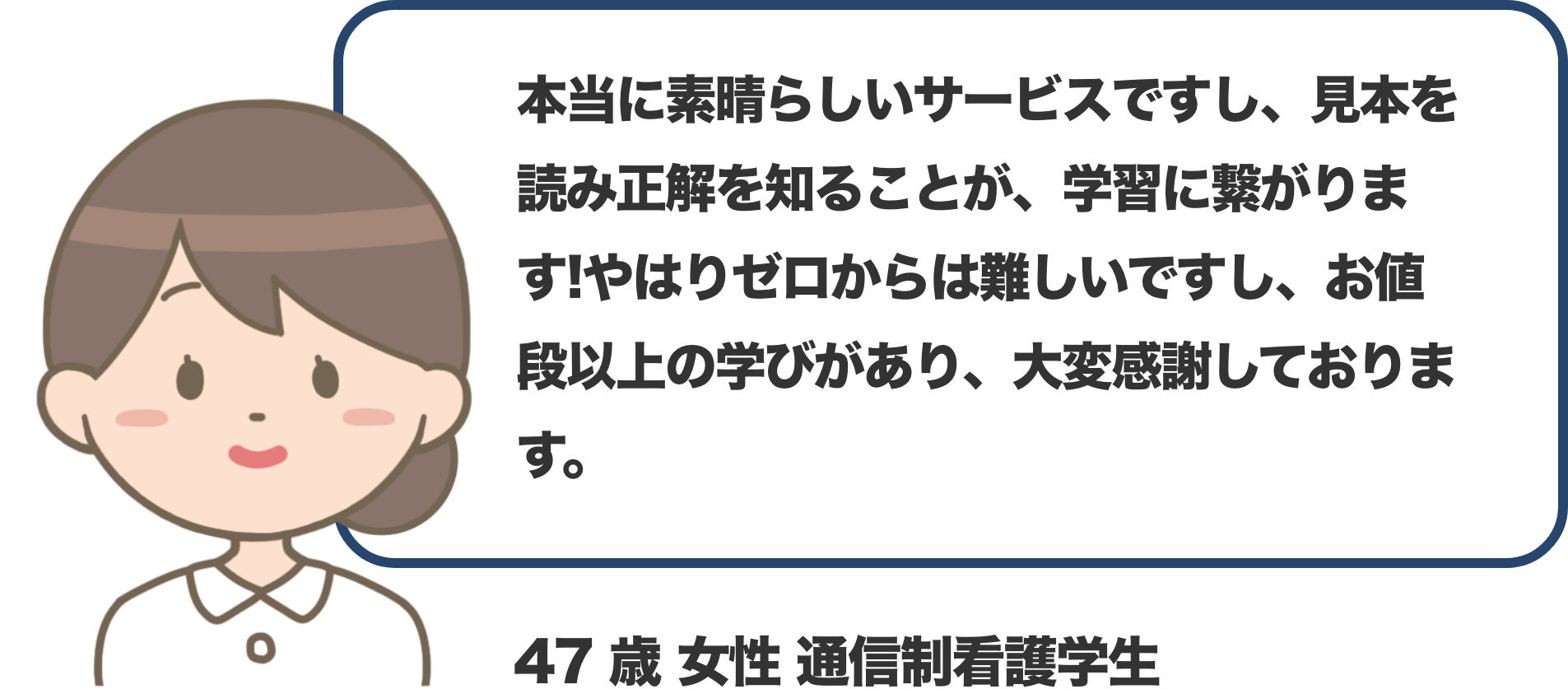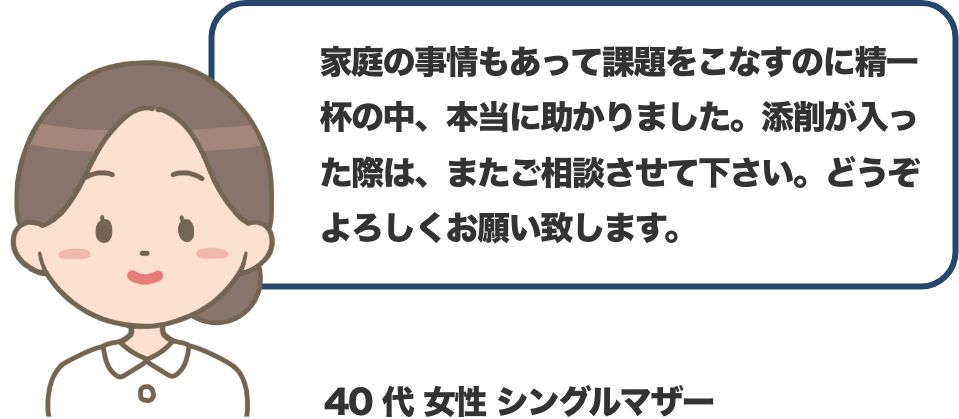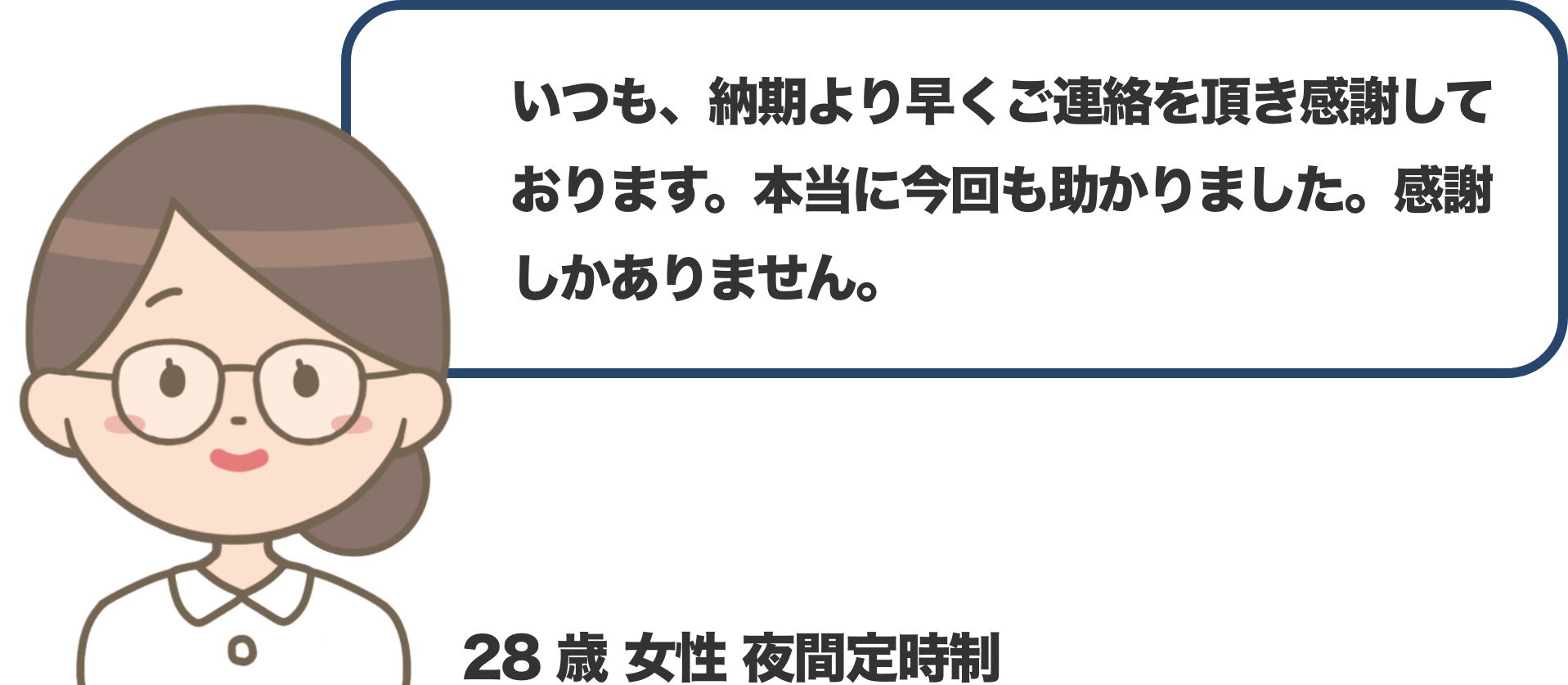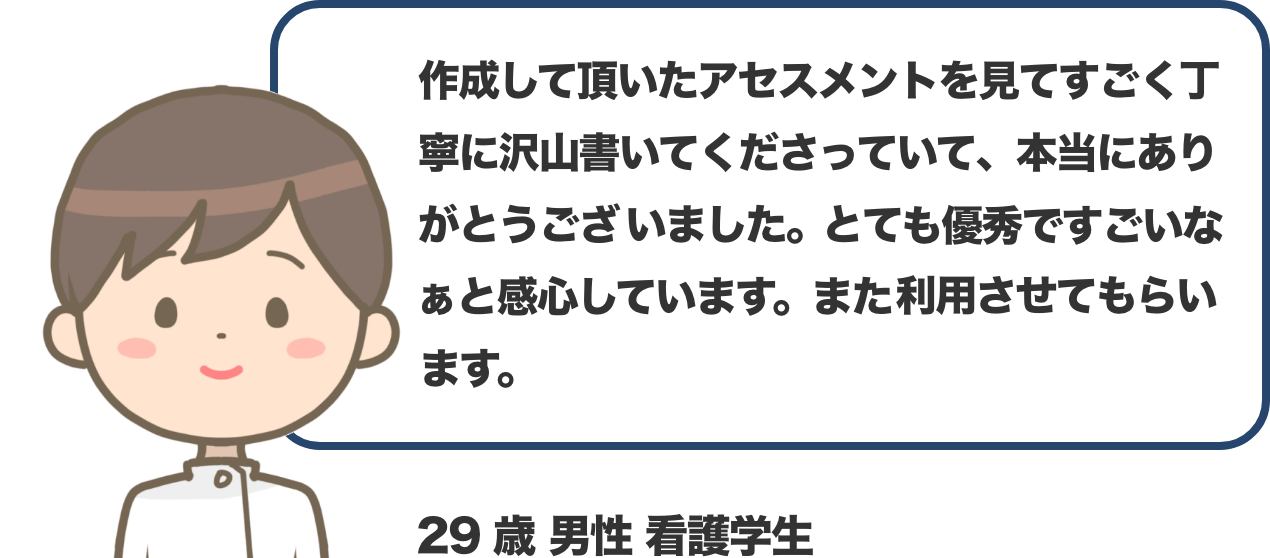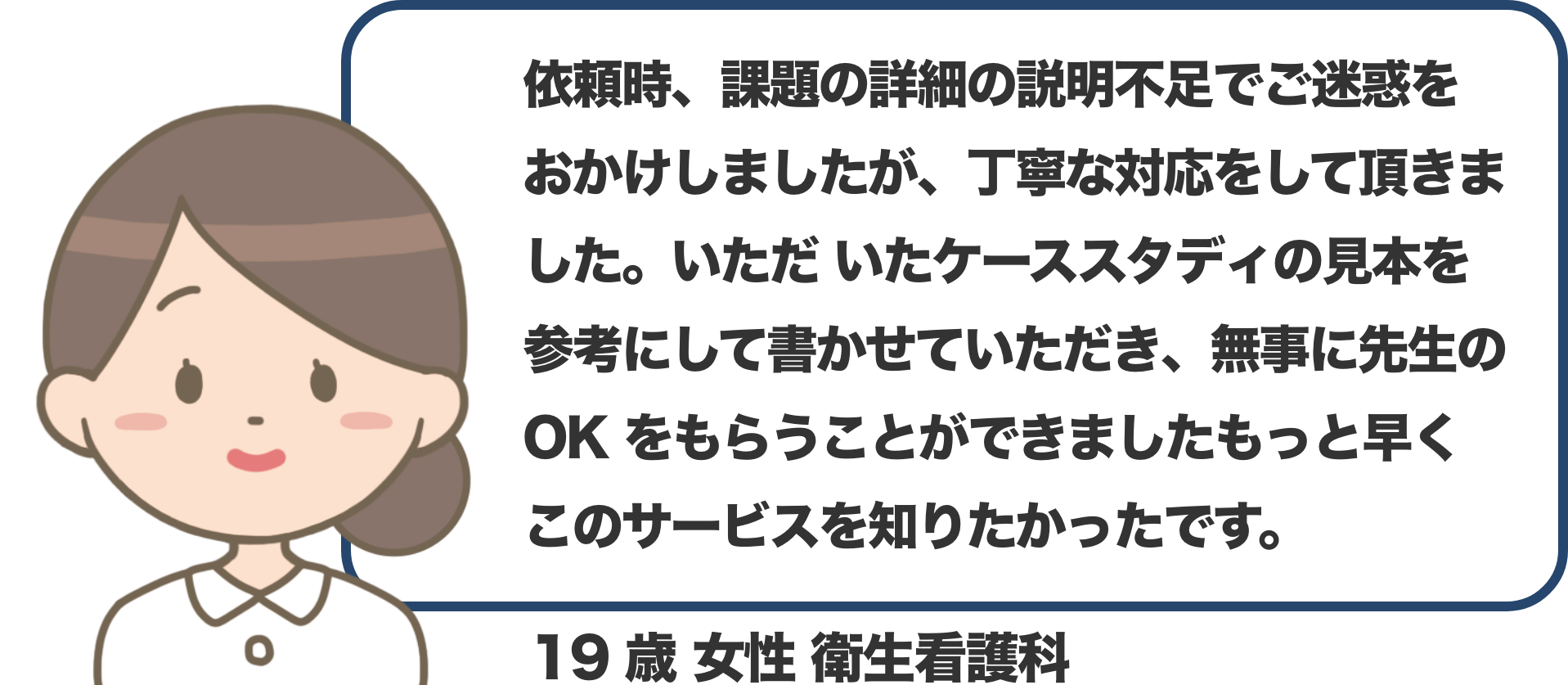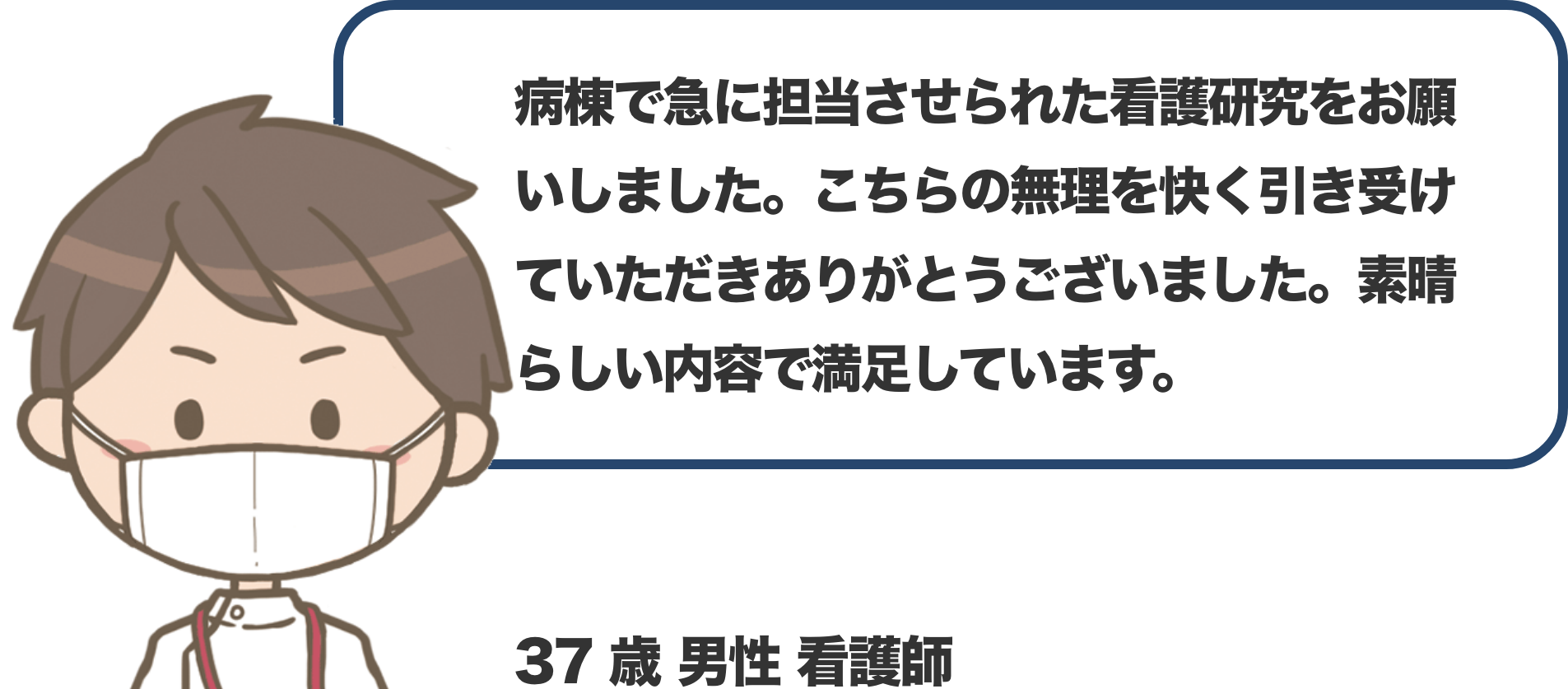病態
原発性肝癌と転移性肝癌とに分類される。肝臓癌の95%が転移性肝癌である。 原発性肝癌とは、肝細胞より発生した癌腫を肝細胞癌(ヘパト-マ)、胆管細胞由来の癌腫を胆管上皮癌(コランジオ-ム)という。未分化の胎児性肝細胞に由来するものを肝芽細胞腫(ヘパブラスト-ム)といい、乳幼児に多い。このうち肝細胞癌が80~90%を占める。また肝細胞癌は肝硬変を合併する場合が多い。 肝細胞癌は肉眼的に塊状型、結節型、瀰漫型の3型に分けられるが、結節型が最も多い。組織学的にはエドモンソンの分類が用いられており、I、II型に比べ、III、IV型では細胞悪性度が高く、脈管内発育が著明で、高率に転移をきたす。肝癌の発育形式では肺や骨などに血行転移をきたしやすいが、門脈を経由しての肝内転移をみることが多く(娘転移)予後に重大な影響を与えている。 原因は、WHOのHBウイルス汚染地区と一致し、肝癌では抗原陽性率が高いことから、HBウイルスが肝癌発生になんらかの影響を及ぼしていると考えられている。また、わが国の肝硬変は肝炎後性の乙型肝硬変が多く、肝硬変患者の1/3に肝癌を併発するといわれ、肝癌患者の60~80%に肝硬変を合併している。 転移性肝癌とは、肝以外の臓器の悪性腫瘍が血行性(門脈、肝動脈)、リンパ行性、あるいは直接浸潤により肝に転移巣を生じたものをいう。
症状
肝癌の症状は次の5つに分けられる
無症状型
肝腫大や超音波検査で発見され、自覚症状の明かでないもの
発熱型
38度以上の発熱をきたすもの
疼痛型
右季肋部痛や肩甲骨下痛などの認められるもの
急性腹症型
肝癌破裂によりショックや腹膜刺激症状を伴うもの
潜伏型
全身衰弱で偶然にあるいは剖検により発見されるもの
他覚的所見は肝硬変の合併が多いため、腹水、脾腫、腹壁静脈怒張などの肝硬変の症状を示すことが多い
検査・診断
肝切除術の術前検査は、肝腫瘍などの範囲、位置、性状などの局在診断と肝予備能および全身状態のチェックに大別される
肝腫瘍などの診断法
超音波検査、X線CT、MRCT、血管造影、シンチグラム、ERCP、PTC、AFP・CEAなどの腫瘍マーカー
一般肝機能検査
トランスアミナーゼ、胆道系酵素、ビリルビン、血清蛋白、ChE、膠質反応、血清脂質、凝固線溶系
肝予備能検査
ICG試験、75gOGTT、ヘパプラスチンテスト
全身状態のチェック
術前一般検査
胸腹部X線撮影、心電図、肺機能検査、腎機能検査、一般血液検査、尿便検査
上部消化管検査
食道静脈瘤、胃十二指腸潰瘍の検索
治療
1.手術療法
肝臓の切除量としては、正常肝の場合で約75%の肝切除が可能である。しかし、本邦の原発性肝癌の大部分をしめる肝細胞癌症例の約90%は肝硬変や慢性肝炎などの慢性肝疾患を合併しており、このような場合では肝予備能が低下しているため肝臓切除量は制約されることになる。すなわち、肝切除術式の決定にさいしては、まず肝予備能を正確に評価し切除可能な肝容量を推測したうえで最も適当な肝切除術式が選択される。
2.肝動脈塞栓療法(TAE)
3.化学療法